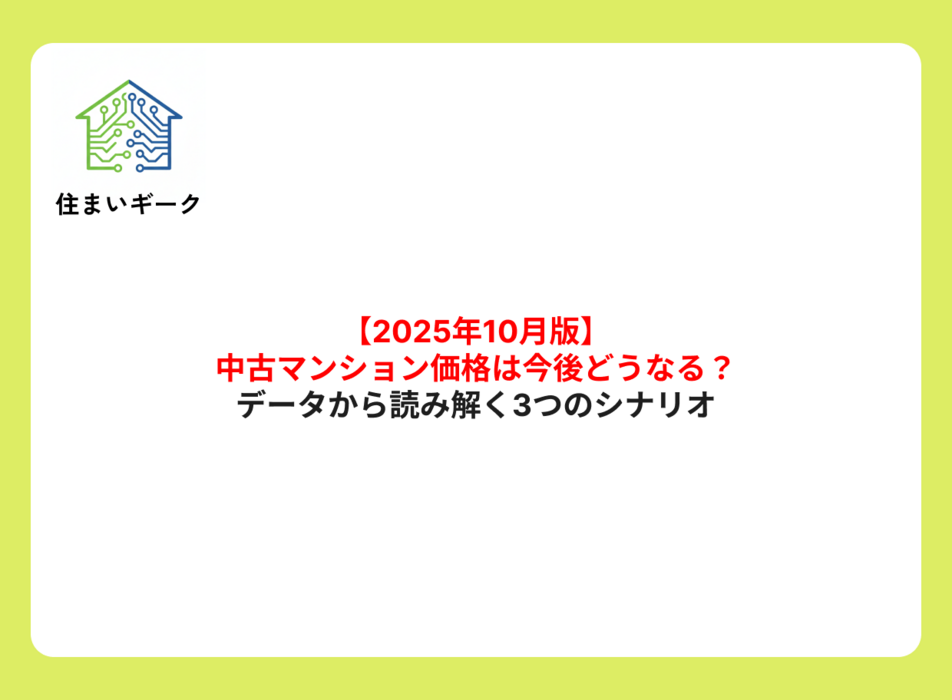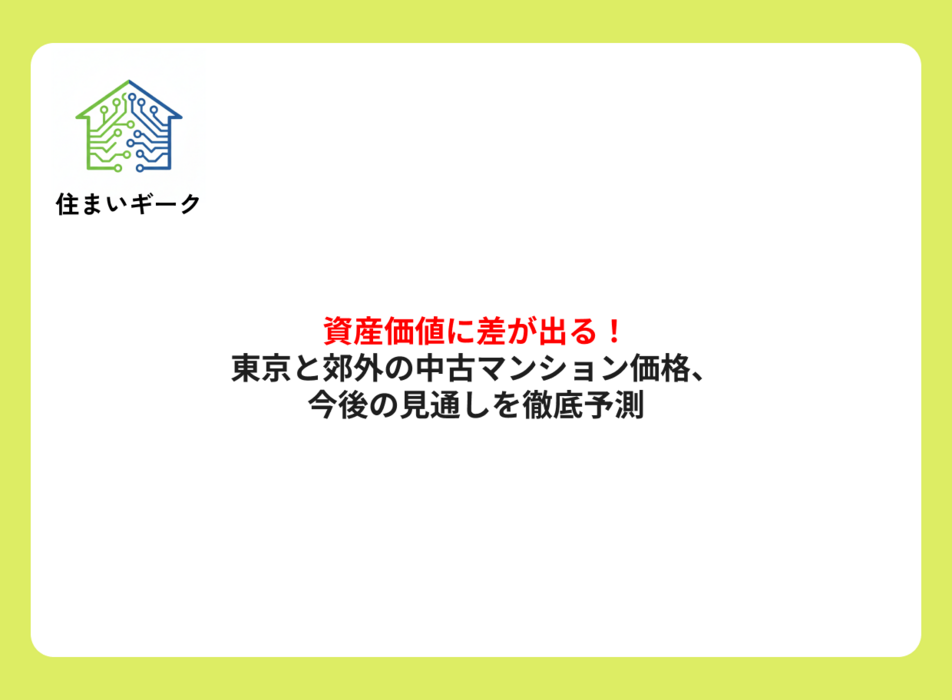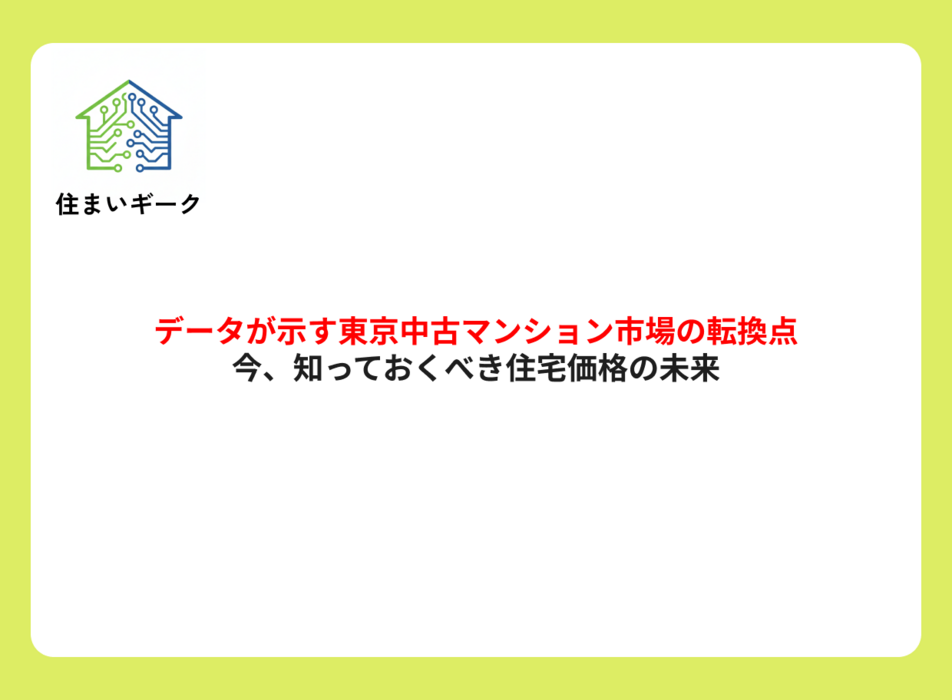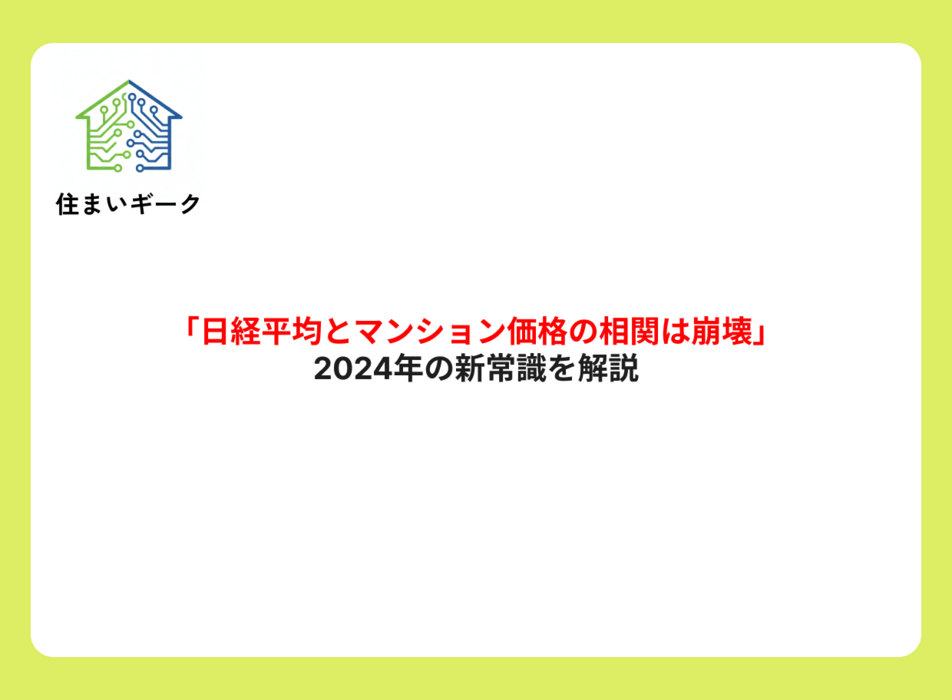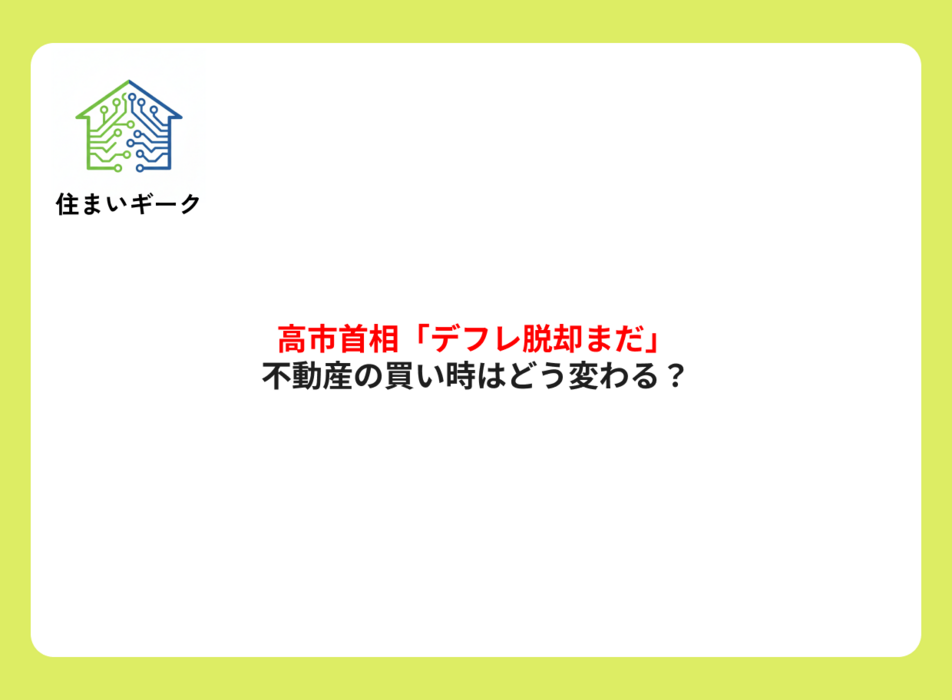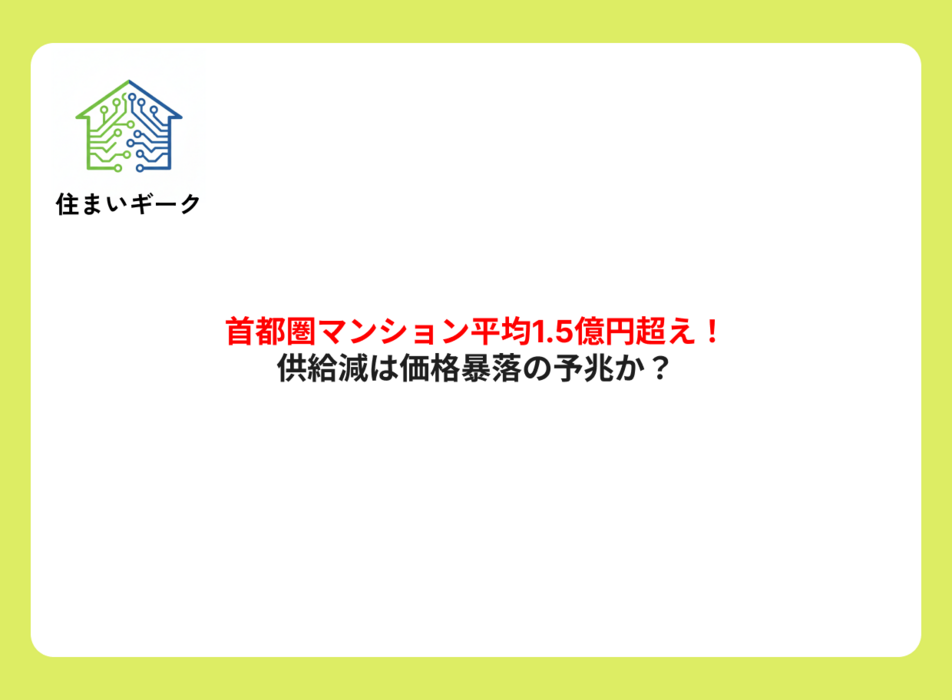1. 2025年10月版:中古マンション価格の最新動向
株式会社東京カンテイが2025年11月20日に発表した最新の調査によると、中古マンション市場は地域によって異なる動きを見せています。首都圏や近畿圏では依然として価格上昇が続いている一方で、中部圏では価格の下落が観測され、市場の方向性が一様ではないことが明らかになりました。本章では、三大都市圏それぞれの具体的な価格動向について、公表されたデータを基に詳しく解説していきます。これらの数値は、今後の市場を読み解く上で基礎となる重要な指標です。
1-1. 首都圏:15ヵ月連続の上昇と牽引する東京都
首都圏における2025年10月の中古マンション平均価格(70㎡換算)は、前月から1.6%上昇し6,115万円に達しました。この上昇は15ヵ月連続となり、市場の力強い基調が継続していることを示しています。前年の同じ月と比較しても25.7%の大幅な上昇となっており、依然として買い手の需要が高い水準で推移していることがうかがえます。この価格上昇は首都圏全域で見られる傾向であり、市場の底堅さを物語る結果と言えるでしょう。
首都圏の中でも特に価格上昇を牽引しているのが東京都です。10月の平均価格は9,478万円で、前月比で1.9%の上昇を記録しました。前年同月比では32.2%もの著しい上昇率を示しており、他のエリアを大きく引き離す形で価格が高騰している状況が鮮明になっています。都心部への需要集中や資産価値の高さが、この力強い価格推移の背景にあると考えられます。
東京都以外の各県も堅調な動きを見せています。神奈川県は前月比0.5%上昇の4,040万円、埼玉県は同じく0.5%上昇して3,043万円となりました。また、千葉県も前月比0.6%プラスの2,837万円となり、いずれも上昇基調を維持しています。これらの周辺県も東京都心へのアクセスの良さなどから安定した需要があり、首都圏全体の価格を押し上げる一因となっているのです。
1-2. 近畿圏:大阪エリアが主導する5ヵ月連続の上昇
近畿圏の中古マンション市場も、首都圏と同様に上昇基調が続いています。2025年10月の平均価格は3,206万円となり、前月比で0.5%上昇しました。これで近畿圏は5ヵ月連続の価格上昇を記録したことになり、安定した市場環境が維持されていることがわかります。前年同月比でも10.5%の上昇となっており、長期的な視点で見ても価格が着実に上昇していることがデータから読み取れます。
この上昇を力強く牽引しているのが大阪府です。10月の平均価格は前月比1.1%上昇の3,765万円に達し、近畿圏全体の平均価格を大きく上回っています。前年同月比の上昇率も17.8%と非常に高く、特に大阪市内を中心としたエリアでの需要の強さが際立っています。再開発の進展や交通利便性の高さが、府内のマンション価格を押し上げる大きな要因となっている模様です。
一方で、同じ近畿圏に属する兵庫県の動きは対照的です。10月の平均価格は2,486万円で、前月から変動はなく横ばいとなりました。前年同月比では1.1%のプラスを維持しているものの、大阪府のような勢いは見られません。このように近畿圏内においても、エリアによって価格動向に明確な差が生じている点は、市場を分析する上で注意すべき重要なポイントです。
1-3. 中部圏:下落に転じ、他圏との違いが鮮明に
首都圏や近畿圏が上昇を続ける中で、中部圏の市場は異なる様相を呈しています。2025年10月の中古マンション平均価格は2,306万円となり、前月から1.2%の下落を記録しました。これは前月の0.5%の下落に続くものであり、中部圏市場が調整局面に入った可能性を示唆しています。前年同月比では1.7%のプラスを維持しているものの、その上昇幅は他の都市圏と比較して著しく小さくなっています。
中部圏の中核である愛知県の平均価格も、前月比0.9%下落の2,437万円となりました。これで愛知県も2ヵ月連続の価格下落となり、中部圏全体の動向を裏付ける結果となっています。名古屋市においても価格は前月比で0.6%下落しており、中心都市でも価格の調整が進んでいることがわかります。他都市圏の上昇基調とは一線を画すこの動きは、中部圏独自の市場要因が影響していると考えられます。
このように、三大都市圏の市場動向を比較すると、首都圏と近畿圏が上昇を維持する一方で、中部圏は下落に転じるという明確な二極化の構図が見て取れます。全国一律のトレンドではなく、地域ごとの特性を詳細に分析することの重要性が、今回のデータから改めて浮き彫りになりました。不動産市場の現状を捉えるためには、こうしたマクロな視点での地域差をまず理解することが不可欠です。
2. データが示す市場の二極化と変化の兆し
最新のデータは、単に価格が上下したという事実だけでなく、市場内部で進行している構造的な変化を示唆しています。具体的には、都心部とそれ以外のエリアにおける「二極化」の深化と、長期間上昇を続けてきたエリアに見られる「変化の兆し」です。本章では、都市別の詳細なデータを基に、これらの市場トレンドをより深く掘り下げて分析します。地域ごとの価格動向の違いや、上昇率の変化に注目することで、今後の市場を見通すための重要なヒントが得られます。
2-1. 都心部への需要集中と顕著な価格上昇
中古マンション市場の価格動向を詳細に見ると、特に需要が都市の中心部に集中している傾向が極めて鮮明に現れています。東京23区の平均価格は1億1,183万円(前月比+1.4%)に達し、これで18ヵ月連続の上昇となりました。この価格水準は、首都圏全体の平均価格である6,115万円を遥かに凌駕しており、いかに需要が23区内に集中しているかを物語っています。
この傾向は、23区をさらに細分化したエリア別データで一層明らかになります。千代田区、中央区、港区などを含む「都心6区」の平均価格は、実に1億7,717万円(前月比+1.0%)もの高値に達しています。このエリアは33ヵ月、つまり3年近くにわたって価格上昇が続いており、資産性の高い都心部への投資需要や実需がいかに根強いかを示しています。利便性やステータス性を求める買い手が、価格上昇を許容してでも都心物件を求めている構図がうかがえます。
同様の現象は近畿圏でも観測されます。大阪市の平均価格は5,427万円(前月比+1.5%)で11ヵ月連続の上昇を記録し、その上昇率は3ヵ月ぶりに1%を超えるなど勢いを増しています。さらに福島区、北区、中央区などを含む「大阪市中心6区」に絞ると、平均価格は8,599万円(前月比+1.7%)に跳ね上がります。このエリアは22ヵ月連続で上昇しており、前年同月比の上昇率では東京の都心6区を上回るほどの力強さを見せています。
2-2. 価格調整が進む郊外・地方都市エリア
都心部が力強い上昇を続ける一方で、一部の郊外や地方都市では価格が調整局面に入っています。この対照的な動きこそが、現在の市場が抱える二極化の本質を示しています。例えば、首都圏に属する千葉市の平均価格は2,636万円となり、前月比で1.5%の下落を記録しました。これは3ヵ月ぶりの下落であり、都心部とは異なる市場サイクルに入った可能性を示唆しています。
近畿圏においても、兵庫県の神戸市が前月比0.1%下落の2,721万円となるなど、都市によって価格動向にばらつきが見られます。大阪市の力強い上昇とは対照的に、一部のエリアでは需要が伸び悩み、価格が頭打ち、あるいは下落に転じている状況が確認できます。これは、買い手の関心がより利便性や将来性の高い中心部に集中し、それ以外のエリアへの波及効果が限定的になっていることの表れかもしれません。
この価格調整の動きが最も顕著なのが中部圏です。名古屋市の平均価格は2,914万円で前月から0.6%下落し、愛知県全体でも価格が下落しています。さらに名古屋市の中心部である「名古屋市中心3区」においても、9月には価格が下落しており、10月に微増(+0.6%)したものの、力強い回復とまでは言えない状況です。このように、都市の規模や中心部であるか否かにかかわらず、価格調整の波が訪れているエリアが存在するという事実は、市場全体を楽観視することへの警鐘と言えるでしょう。
2-3. 上昇エリアに潜む「上昇率の鈍化」という変化
長らく価格上昇が続いてきたエリアにおいても、その勢いに変化の兆しが見られます。具体的には「上昇率は縮小・鈍化傾向にある」という点です。これは市場が新たなフェーズに移行しつつある可能性を示す重要なサインと言えます。例えば、18ヵ月連続で上昇している東京23区ですが、10月の前月比上昇率+1.4%という数値は、9月の+2.9%や8月の+2.3%と比較すると明らかに勢いが弱まっています。
この上昇ペースの鈍化は、他の主要都市でも同様に観測されています。横浜市の10月の上昇率は+0.3%で、9月の+1.5%から大幅に縮小しました。さいたま市も同様に、9月の+2.2%から10月は+0.2%へと上昇ペースが大きく鈍化しています。東京カンテイのレポートでも、これらの都市について「上昇傾向ですが、23区同様に鈍化しています」と指摘されており、市場の過熱感が和らぎつつあることがうかがえます。
価格上昇のペースが鈍化している背景には、価格が高値圏に達したことによる買い手の購買意欲の減退や、高値への警戒感が広がっている可能性が考えられます。物件価格が上昇し続けた結果、購入できる層が限定的になり、需要の伸びしろが小さくなってきたのかもしれません。この「上昇率の鈍化」という現象は、今後の価格動向が横ばいや下落に転じる前触れとなる可能性もあり、極めて注意深く見守るべき変化の兆しと言えるでしょう。
3. 中古マンション市場の今後の展望と予測シナリオ
現在の市場動向を踏まえると、今後の中古マンション市場は複数のシナリオが考えられます。都心部と郊外の二極化が継続するのか、それとも金融政策などの外部要因によって市場全体が新たな局面を迎えるのか、その見通しは一様ではありません。本章では、これまでのデータ分析に基づき、今後想定される3つの主要なシナリオを提示し、それぞれの展開の可能性と背景にある要因について具体的に考察していきます。
3-1. シナリオ1:都心堅調・郊外調整の二極化が継続
最も可能性が高いと考えられるのが、現在見られる二極化の構図が今後も継続するというシナリオです。つまり、東京の都心6区や大阪市中心6区といった資産性・利便性の高い中心部の価格は堅調に推移する一方で、すでに調整局面に入っている郊外や地方都市では、価格の横ばい、あるいは緩やかな下落が続くという展開です。このシナリオの根拠は、都心部の価格を支える需要の根強さにあります。
東京の都心6区が33ヵ月、大阪市中心6区が22ヵ月という極めて長期間にわたって価格上昇を続けている事実は、単なる一時的なブームではなく、構造的な需要が存在することを示しています。職住近接を求める実需層や、国内外の投資家からの資金流入が、都心部の価格を強力に下支えしていると考えられます。東京カンテイのレポートでも、都心6区のトレンドは引き続き堅調と分析されており、この流れがすぐに反転するとは考えにくい状況です。
一方で、名古屋市や千葉市のようにすでに価格が下落に転じているエリアでは、この調整の動きが継続する可能性が高いでしょう。価格上昇期に都心部との価格差から選ばれていた郊外エリアも、価格が高くなりすぎたことで割安感が薄れ、買い手の関心が再び都心部へと回帰している可能性があります。また、金利の上昇懸念などが広がれば、予算に制約のある層が多い郊外エリアから先に購買意欲が減退し、価格調整の圧力はさらに強まることも想定されます。
3-2. シナリオ2:金融政策の変動による市場全体の調整
次に考えられるのが、金融政策の変更、特に金利の上昇が不動産市場全体に影響を及ぼし、多くのエリアで価格が調整局面に入るというシナリオです。現在の不動産価格の上昇は、長年にわたる歴史的な低金利環境に支えられてきた側面が非常に大きいと言えます。住宅ローン金利が低水準で推移してきたからこそ、多くの人々が高額な不動産を購入することが可能でした。
もし将来的に、政策金利の引き上げなどによって住宅ローン金利が上昇局面に転じた場合、購入者の返済負担は増大します。これにより、これまでと同じ価格の物件でも月々の返済額が上がり、結果として購入できる物件価格の上限が下がることになります。これは不動産市場における実質的な購買力の低下を意味し、買い手の需要を冷え込ませる直接的な要因となり得ます。
この影響は、特に価格が高騰している都心部においても無縁ではありません。これまで上昇を続けてきたエリアほど、価格下落の幅が大きくなる可能性も否定できません。特に、返済額の変動リスクを抱える変動金利でローンを組んでいる層が多い現状では、金利上昇は家計に直接的な打撃を与えます。その結果、買い控えや、場合によっては返済困難による売り物件の増加が市場全体の価格を押し下げるという展開も十分に考えられるでしょう。
3-3. シナリオ3:一部エリアにおける局地的な価格再上昇
最後に、市場全体が調整局面に向かう中でも、特定の要因を持つ一部のエリアでは局地的に価格が再上昇するというシナリオも考えられます。その最大の要因として挙げられるのが、インバウンド需要の本格的な回復と、それに伴う海外投資家からの資金流入です。円安が進行している現在の状況は、海外の投資家にとって日本の不動産が相対的に割安に見えるため、投資対象としての魅力を高めています。
特に、国際的な知名度が高い東京の都心部や、京都、大阪、あるいは北海道のニセコといった観光地に近いエリアの高級マンションは、海外の富裕層にとって魅力的な投資先となります。彼らの投資目的は居住用だけでなく、賃貸運用や将来的なキャピタルゲイン(売却益)を狙ったものが多く、国内の景気や金利動向とは異なるロジックで資金が流入する可能性があります。
こうした海外からの投資マネーが特定のエリアに集中した場合、その地域の物件需要が喚起され、周辺の市場動向とは関係なく価格が押し上げられることが想定されます。例えば、東京の都心6区や大阪市中心6区で見られる高い前年同月比の上昇率の背景には、すでにこうした動きが影響している可能性も考えられます。今後、国際的な往来がさらに活発化すれば、この局地的な価格上昇の動きがより鮮明になるかもしれません。
4. 不動産購入検討者が取るべき賢明な判断とは
地域による二極化や価格上昇の鈍化など、中古マンション市場が複雑な様相を呈する中で、購入を検討している方々はどのような戦略を取るべきでしょうか。画一的な「買い時」というものは存在せず、個々の状況に応じた冷静かつ戦略的なアプローチがこれまで以上に求められます。本章では、現在の市場環境を踏まえ、不動産購入検討者が取るべき3つの具体的な行動指針について、ステップごとに詳しく解説していきます。
4-1. ステップ1:希望エリアのミクロな市場動向を把握する
まず最も重要なのは、マクロな市場全体の動向に一喜一憂するのではなく、自身が購入を希望するエリアのミクロな市場動向を徹底的に調査することです。今回のデータが示すように、同じ首都圏内でも東京23区と千葉市では価格の方向性が全く異なり、近畿圏でも大阪市と神戸市では対照的な動きを見せています。したがって、「首都圏の価格が上昇しているから」といった広域のデータだけで判断するのは極めて危険です。
具体的な調査方法としては、まず市区町村単位での価格推移を確認することが挙げられます。さらに一歩進んで、検討している最寄り駅周辺の売り出し物件の価格や、過去の成約価格のデータを調べることが不可欠です。不動産情報サイトや国土交通省が提供する「不動産取引価格情報検索」などを活用すれば、個人でもある程度の相場観を養うことが可能です。
また、そのエリアで売りに出されている物件の数(在庫数)が、増えているのか減っているのかも重要な指標となります。在庫数が増加傾向にあれば、買い手市場に傾きつつあり、価格交渉がしやすくなる可能性があります。逆に在庫数が減少していれば、売り手市場が続いており、価格が下がりにくい状況かもしれません。このように、希望エリアを絞り込み、その地域固有の需給バランスを詳細に把握することが、賢明な判断を下すための第一歩となります。
4-2. ステップ2:自身のライフプランと資金計画を再検証する
次に、市場の動向と並行して、自身のライフプランや資金計画を改めて厳格に検証することが求められます。特に、今後の金利上昇リスクは、資金計画において最大限考慮すべき重要な要素です。現在は低金利が続いていますが、将来的に金利が上昇した場合でも、家計が破綻することなく住宅ローンの返済を続けられるか、複数のシナリオを想定してシミュレーションしておく必要があります。
例えば、変動金利でローンを組む場合は、金利が1%あるいは2%上昇した場合の月々の返済額と総返済額がどの程度増加するのかを具体的に計算し、その負担増に耐えられるだけの余裕が家計にあるかを確認すべきです。もし余裕がないのであれば、購入価格の上限を見直すか、金利変動リスクのない全期間固定金利のローンを選択するといった判断が必要になります。
さらに、物件の資産価値の変動もライフプランに大きく影響します。特に、将来的に売却や買い替えを視野に入れている場合は、購入を検討している物件の資産価値が維持されやすいか、あるいは下落しにくいかという視点が重要です。駅からの距離、周辺環境、建物の管理状態といった要素は、将来の資産価値を左右します。市場が不安定な時期だからこそ、目先の価格変動だけでなく、10年後、20年後を見据えた長期的な視点で物件を選び、無理のない資金計画を立てることが肝要です。
4-3. ステップ3:複数の物件を比較し、適正価格を見極める
最後に、具体的な物件探しの段階では、焦って一つの物件に飛びつくことなく、必ず複数の物件を比較検討し、適正な価格を見極める目を養うことが重要です。特に、東京23区などの人気エリアで見られる上昇率の鈍化は、市場が価格の高値圏にあることを示唆しています。このような状況下で冷静な判断を欠くと、いわゆる「高値掴み」をしてしまうリスクが高まります。
物件を比較する際には、単に価格や広さ、間取りといったスペックだけでなく、建物の管理状態や修繕履歴、長期修繕計画の内容などを必ず確認しましょう。同じような条件の物件でも、管理状態によって将来の資産価値や追加で発生する費用は大きく変わってきます。複数の物件の内覧を経験することで、物件ごとの長所や短所を客観的に比較できるようになり、売り出し価格が周辺相場や物件価値に対して妥当であるかを判断する精度が高まります。
また、価格交渉の余地を探ることも重要です。売り出しから長期間が経過している物件や、周辺に競合となる類似物件が多く存在する場合には、価格交渉に応じてもらえる可能性があります。そのためにも、希望エリアの相場観を事前にしっかりと把握しておくことが前提となります。市場の動向に流されることなく、自分自身の基準で物件の価値を冷静に評価し、納得できる価格での購入を目指す姿勢が、最終的に後悔のない不動産購入につながるのです。
出展元
*株式会社東京カンテイ, "三大都市圏・主要都市別/中古マンション70㎡価格月別推移", 2025年11月20日