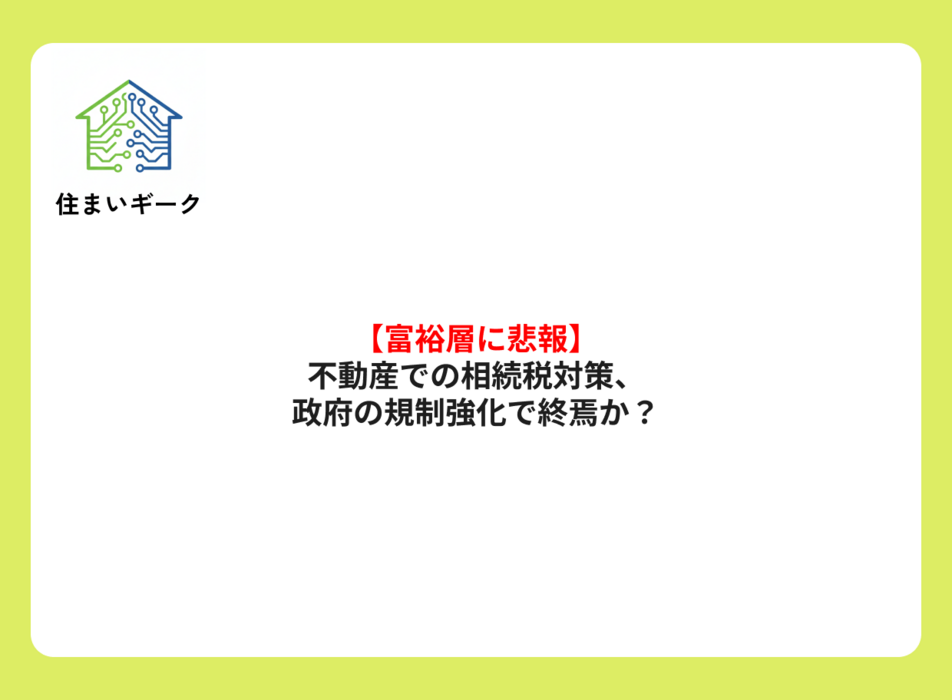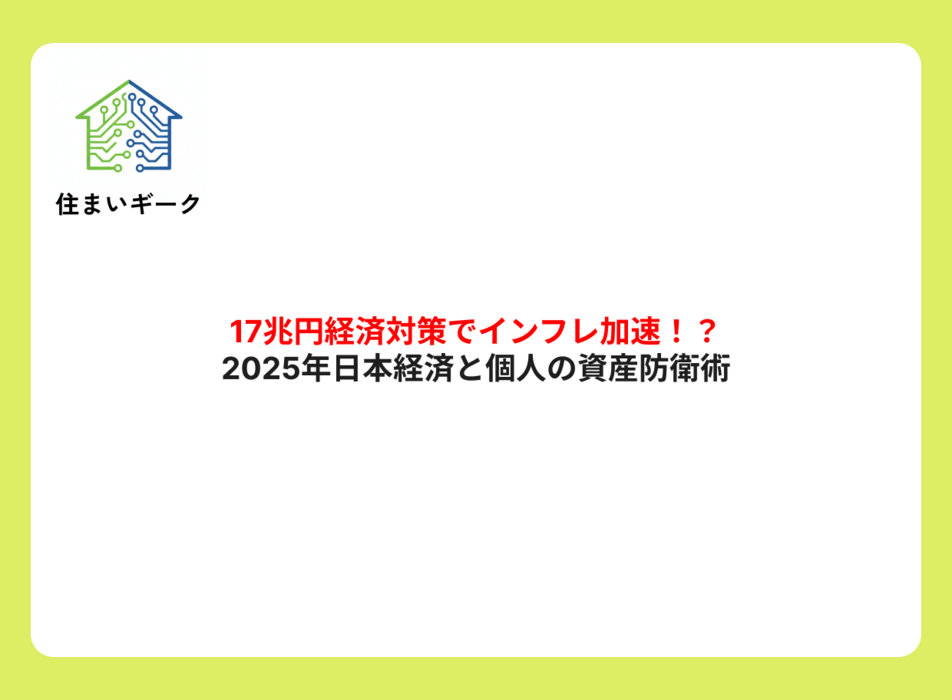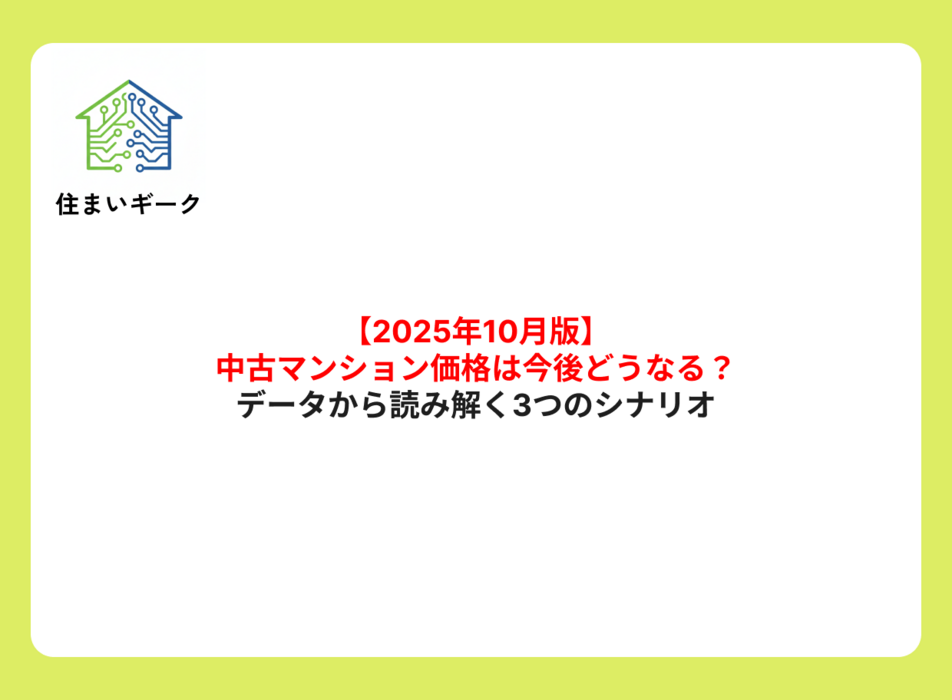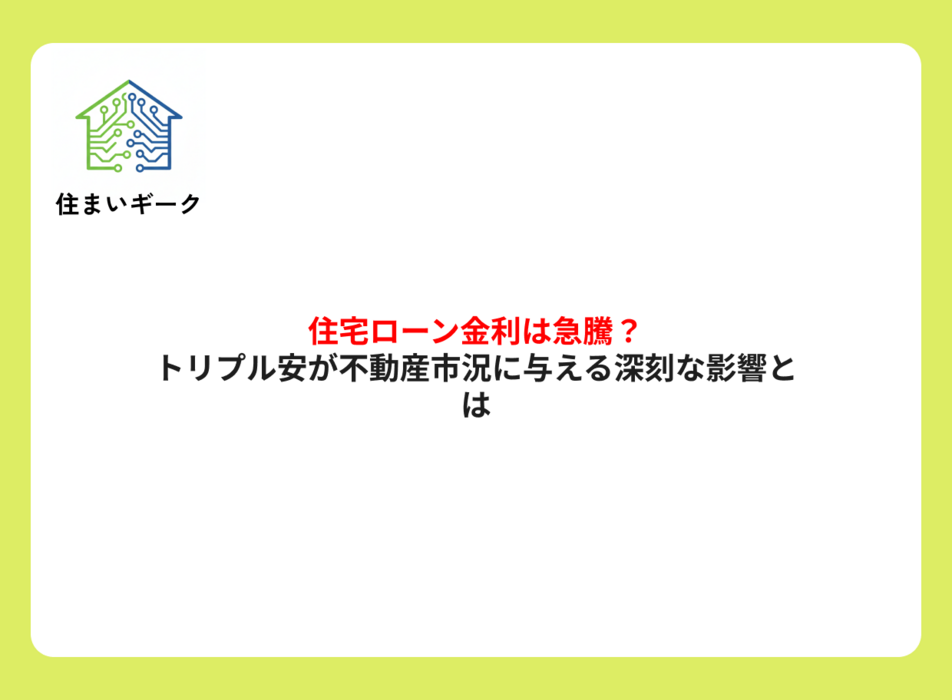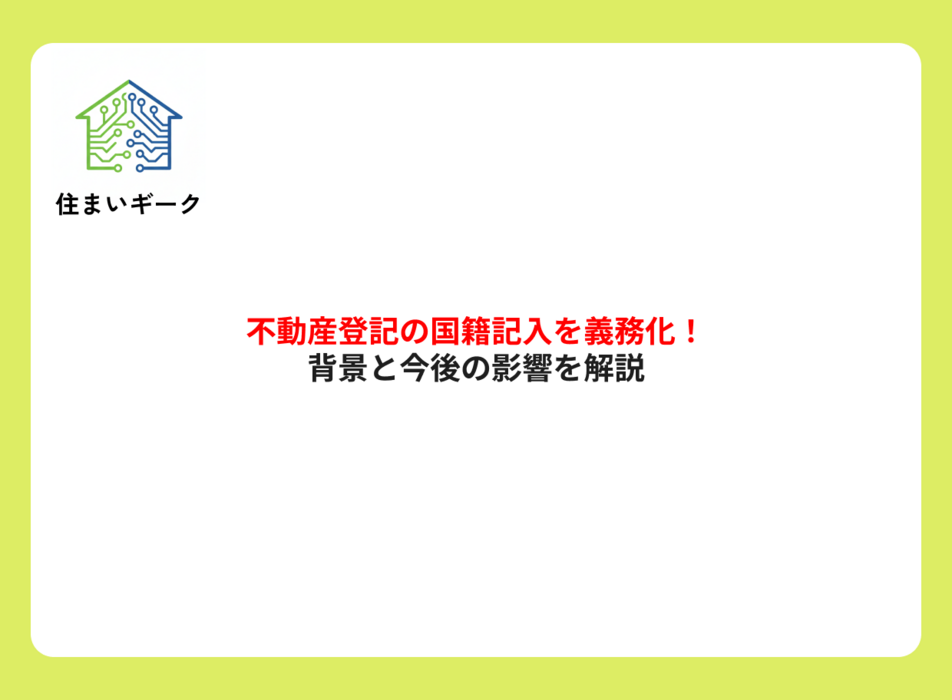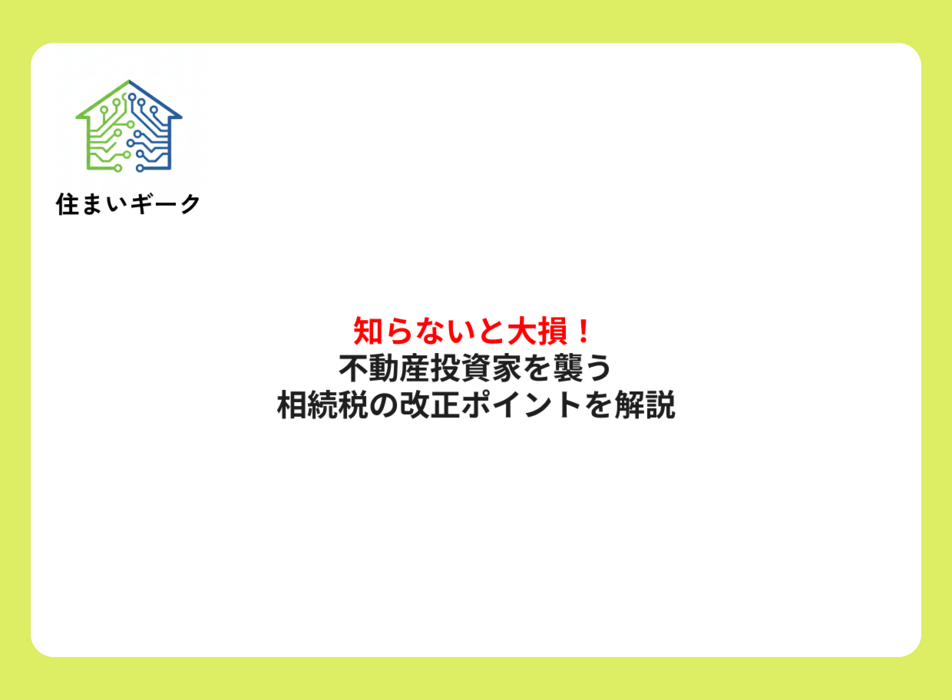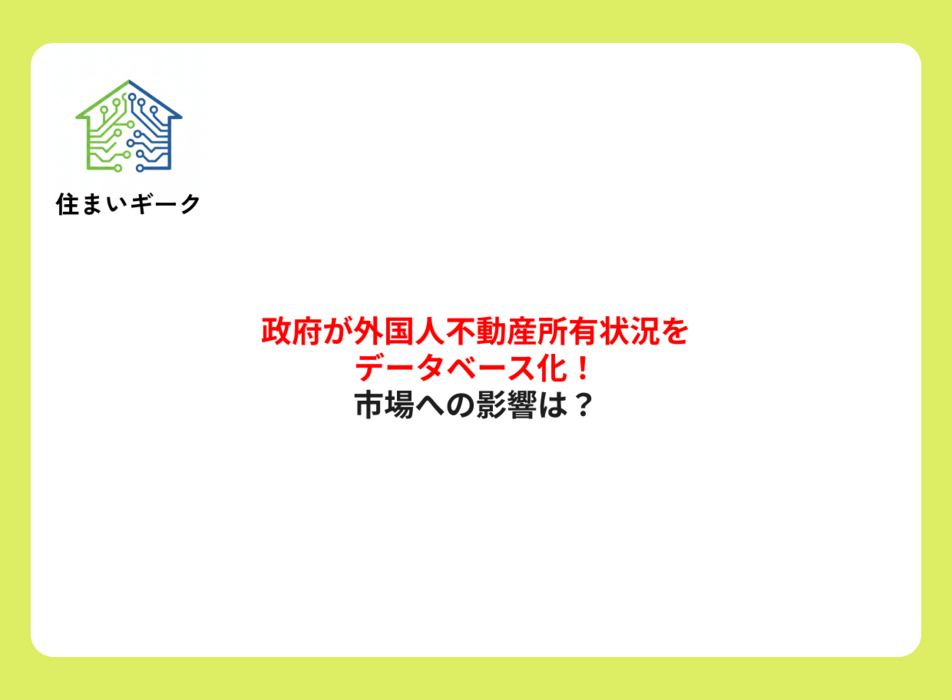1. 注目される不動産投資と相続税対策の動向
近年、相続税対策の一環として不動産投資が注目を集めています。特に賃貸マンションの一棟買いは、大きな節税効果が期待できる手法です。しかし、この節税効果に対し、政府が対策に乗り出す可能性が浮上しました。本記事では、賃貸マンション投資による相続税節税の仕組みを解説します。その上で、政府の税制調査会での議論が、今後の市場に与える影響を考察します。
1-1. 相続税評価額の圧縮が節税の鍵
相続税は、亡くなった方から受け継いだ財産の総額に対して課税されます。その財産の価値を算出する基準が「相続税評価額」と呼ばれるものです。現金や預金は額面通りの金額がそのまま相続税評価額として扱われます。一方で、不動産の相続税評価額は実際の取引価格よりも低く算定されます。この評価額の差を利用することが、不動産による相続税対策の基本です。
1-2. 土地と建物の評価方法
土地の相続税評価額は、主に国税庁が定める「路線価」を基に計算されます。路線価は、主要な道路に面した土地1平方メートルあたりの価格を示したものです。一般的に、実際の取引価格である時価の8割程度が目安とされています。建物については、市町村が固定資産税を算出するために用いる「固定資産税評価額」が基準です。これは建築費用の5割から7割程度になることが一般的とされています。
2. 賃貸マンション一棟買いの具体的な節税効果
現金を不動産、特に賃貸物件に換えることで、相続税評価額はさらに低くなります。ここでは賃貸マンションの一棟買いが、なぜ高い節税効果を生むのかを解説します。賃貸に供することで適用される評価額の軽減措置が重要なポイントとなります。この仕組みを理解することで、節税効果の本質が見えてきます。
2-1. 「貸家建付地」による土地評価額の軽減
自身が所有する土地の上に建てた建物を第三者に賃貸している場合、その土地は「貸家建付地(かしやたてつけち)」として評価されます。土地の所有者は、入居者がいる限り自由にその土地を使用することができません。この利用上の制約が考慮され、更地の状態よりも相続税評価額が低くなります。評価額は以下の計算式で算出され、更地の場合よりも低く抑えられます。
貸家建付地の評価額 = 自用地としての評価額 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
借地権割合や借家権割合は地域によって異なりますが、この計算により土地の評価額がさらに15%から20%程度圧縮される効果が期待できます。
2-2. 「貸家」による建物評価額の軽減
賃貸に利用されている建物そのものも「貸家(かしや)」として評価が下がります。こちらも土地と同様に、入居者がいることで所有者の自由な使用が制限されるためです。建物の固定資産税評価額から、借家権割合に相当する金額が控除されます。全国一律で借家権割合は30%と定められており、計算式は以下の通りです。
貸家の評価額 = 固定資産税評価額 × (1 - 借家権割合 × 賃貸割合)
この規定により、自己使用の建物に比べて評価額が30%軽減されます。
2-3. 節税効果のシミュレーション
仮に現金1億円を相続する場合、相続税評価額はそのまま1億円です。一方、同じ1億円で賃貸マンション(土地5,000万円、建物5,000万円)を購入した場合を考えます。土地の路線価が時価の8割、建物の固定資産税評価額が時価の7割と仮定します。
まず、不動産に換えた時点で評価額は下がります。
土地評価額:5,000万円 × 80% = 4,000万円
建物評価額:5,000万円 × 70% = 3,500万円
合計評価額:7,500万円
次に、この物件をすべて賃貸に出している場合の評価額を計算します。
※借地権割合60%、借家権割合30%と仮定
土地(貸家建付地):4,000万円 × (1 - 60% × 30%) = 3,280万円
建物(貸家):3,500万円 × (1 - 30%) = 2,450万円
合計評価額:5,730万円
このシミュレーションでは、現金1億円が賃貸マンションに形を変えることで、相続税評価額が5,730万円まで圧縮されました。実に4,270万円もの評価額引き下げ効果が生まれる計算となります。これが賃貸マンション一棟買いによる節税効果の具体的な仕組みです。
3. 政府による節税対策強化の動き
これまで有効とされてきた不動産による相続税対策ですが、その状況に変化が生じる可能性があります。政府の税制調査会が、この節税スキームについて議論を開始したことが明らかになりました。行き過ぎた節税と見なされるケースに対し、国が規制に乗り出す可能性が指摘されています。
3-1. 税制調査会での議論開始
日本経済新聞は2025年1月14日付の記事で、政府の税制調査会が不動産を活用した相続税の節税策について議論したと報じました。記事内では、国税庁が賃貸マンションの一棟買いなどの事例で節税効果が大きいと指摘したとされています。この動きは、今後の税制改正で相続税評価額の算定方法が見直される可能性を示唆するものです。
出展: 日本経済新聞 2025年1月14日「相続税、不動産節税の議論開始 政府税調、賃貸マンション念頭」
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA133CV0T11C25A1000000/
3-2. 対策強化の背景にある問題意識
なぜ今、政府は対策の議論を始めたのでしょうか。その背景には、実際の取引価格と相続税評価額の間に著しい乖離が生じているケースへの問題意識があります。特に、都心部のタワーマンションなどを利用した節税は「タワマン節税」と呼ばれ、かねてより問題視されてきました。国税当局は、相続直前に不動産を購入・売却するなど、租税回避が目的と見なされる行為には厳しい姿勢で臨んでいます。過去には、路線価による評価を認めず、時価で追徴課税した事例で国が勝訴した最高裁判決も出ています。
4. 今後想定される規制と市場への影響
税制調査会での議論が進めば、将来的には相続税評価額の算定ルールそのものが見直される可能性があります。規制が強化された場合、不動産投資家や市場全体にどのような影響が及ぶのか、考えられるシナリオを考察します。投資戦略の見直しが迫られることになるかもしれません。
4-1. 考えられる具体的な規制内容
最も可能性が高い規制内容は、相続税評価額の算定ルールの見直しです。現行の路線価や固定資産税評価額を基準とする画一的な評価方法ではなく、実際の取引価格をより反映させる仕組みが導入されることが考えられます。例えば、不動産鑑定士による鑑定評価額を基準としたり、時価と評価額の乖離率が大きい場合に評価額を補正する新たな規定が設けられたりする可能性があります。このような改正が行われれば、これまでのような大きな評価額の圧縮は期待できなくなります。
4-2. 不動産投資家と市場への影響
規制強化は、相続税対策を主目的とする不動産投資の魅力を大きく損なう可能性があります。特に、これまで節税メリットを重視して高額な収益物件を購入してきた富裕層の投資意欲が減退することが予想されます。その結果、都心部の一棟マンションや商業ビルといった物件の需要が低下し、価格に影響を及ぼすことも考えられます。一方で、節税目的ではなく、純粋な利回りや資産価値を重視した不動産投資の重要性が相対的に高まることになるでしょう。
4-3. これからの相続税対策のあり方
今後の税制改正の動向を注視しつつ、相続税対策の考え方を見直す必要があります。不動産投資を行う際は、節税効果だけに依存するのではなく、長期的に安定した家賃収入が見込めるか、資産価値が維持されやすいかといった収益性の観点がより重要になります。また、生命保険の非課税枠の活用や、暦年贈与・相続時精算課税制度といった生前贈与の仕組みなど、不動産以外の選択肢も組み合わせた総合的な対策を検討することが求められます。どのような対策が最適かは個々の資産状況によって異なるため、税理士などの専門家へ相談することが不可欠です。