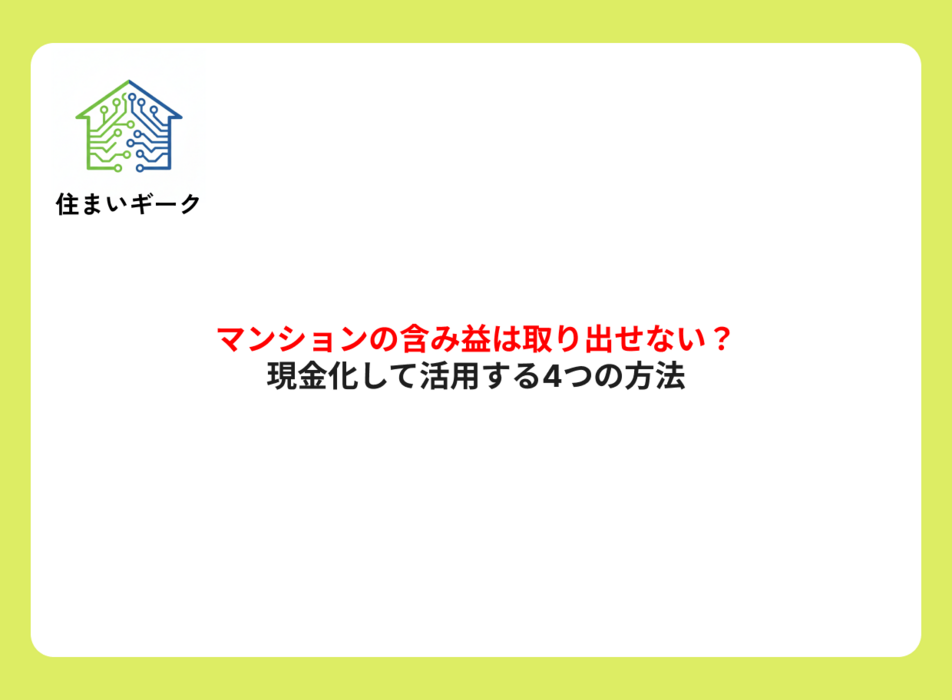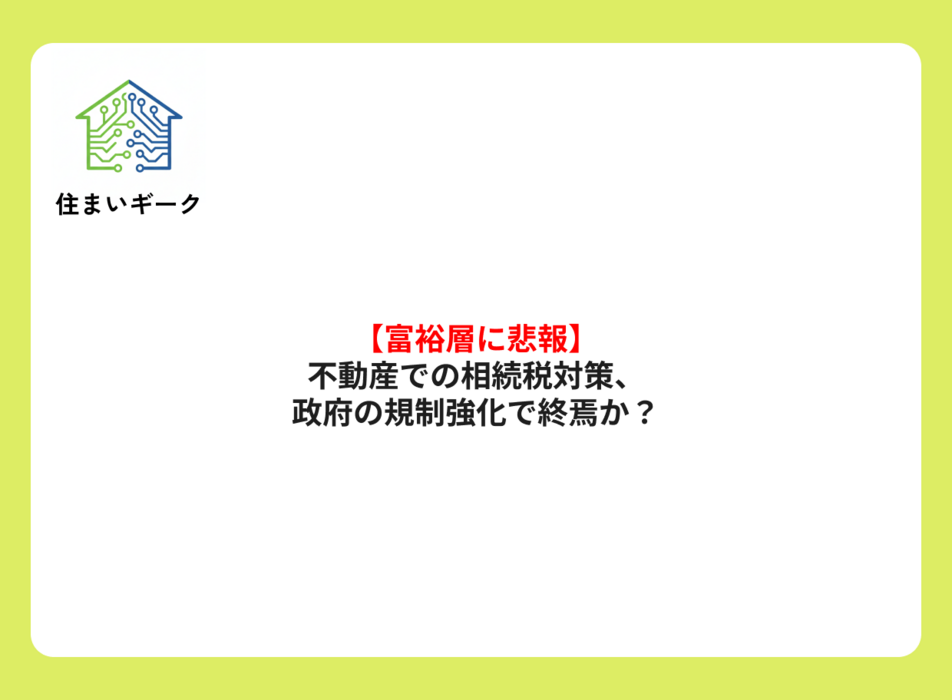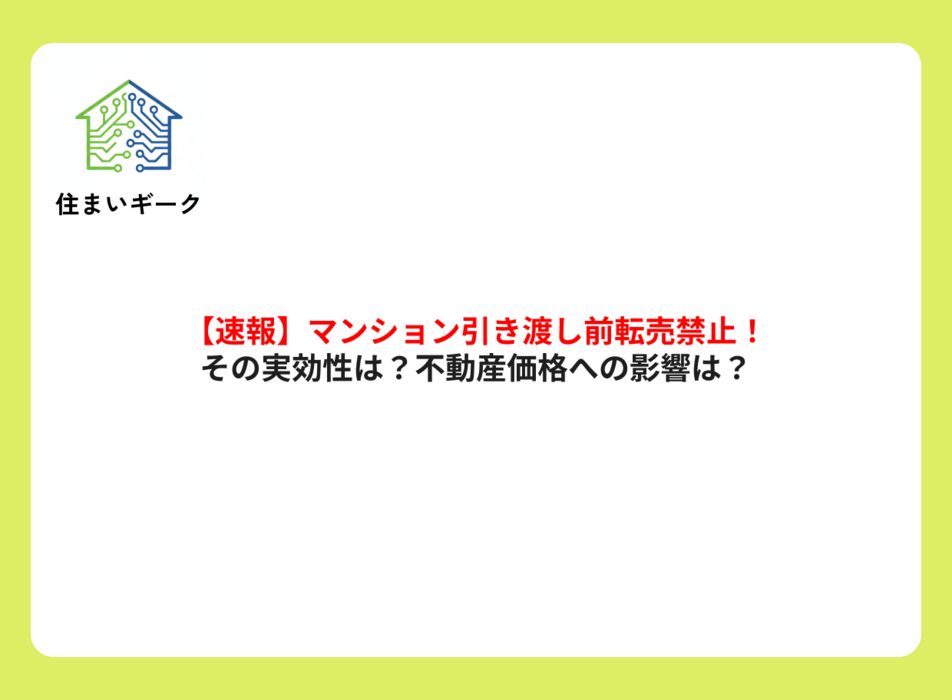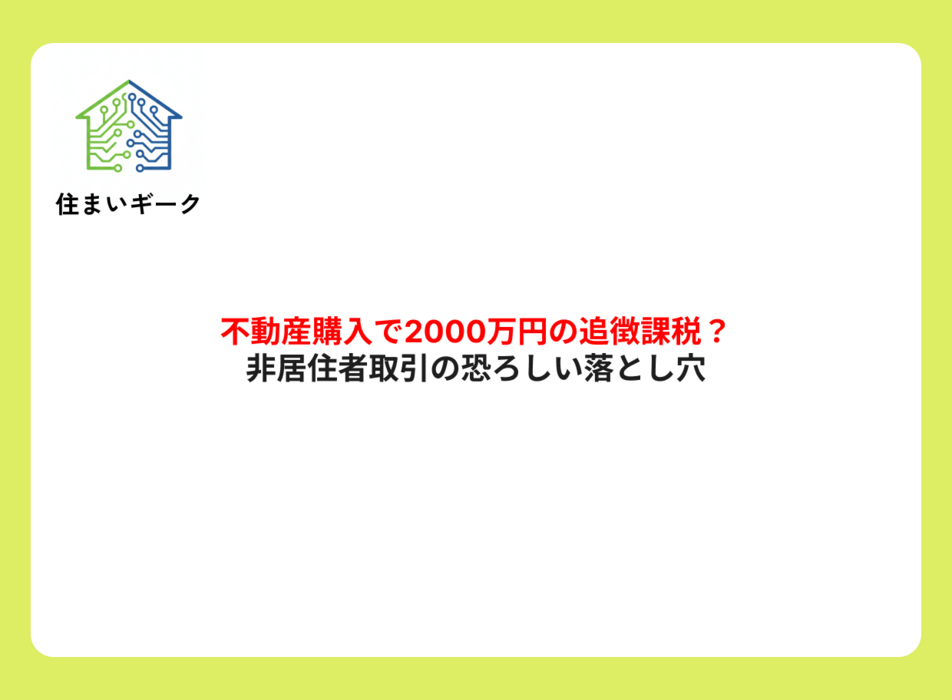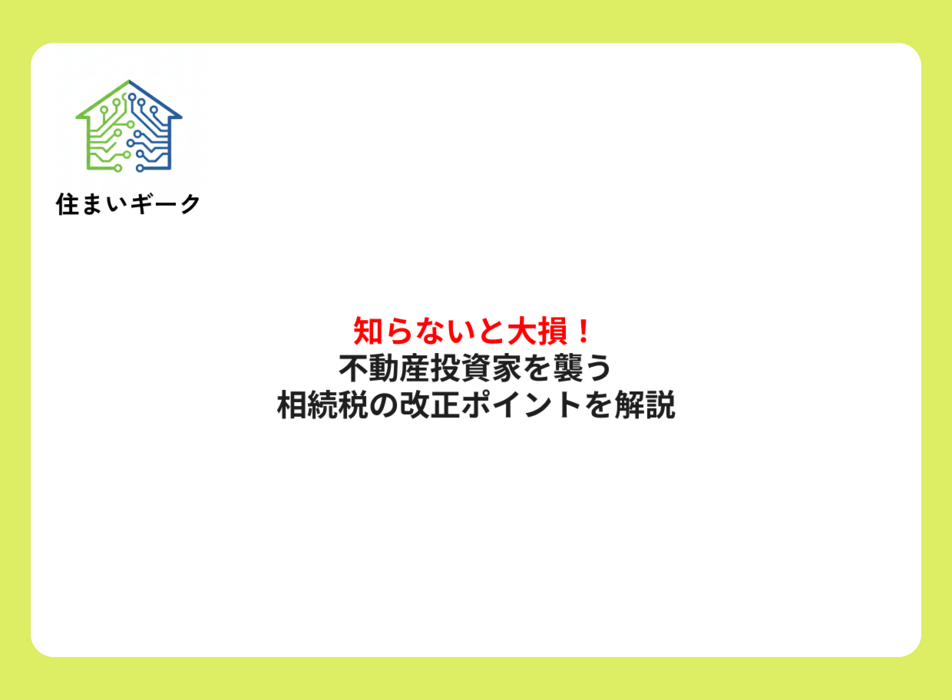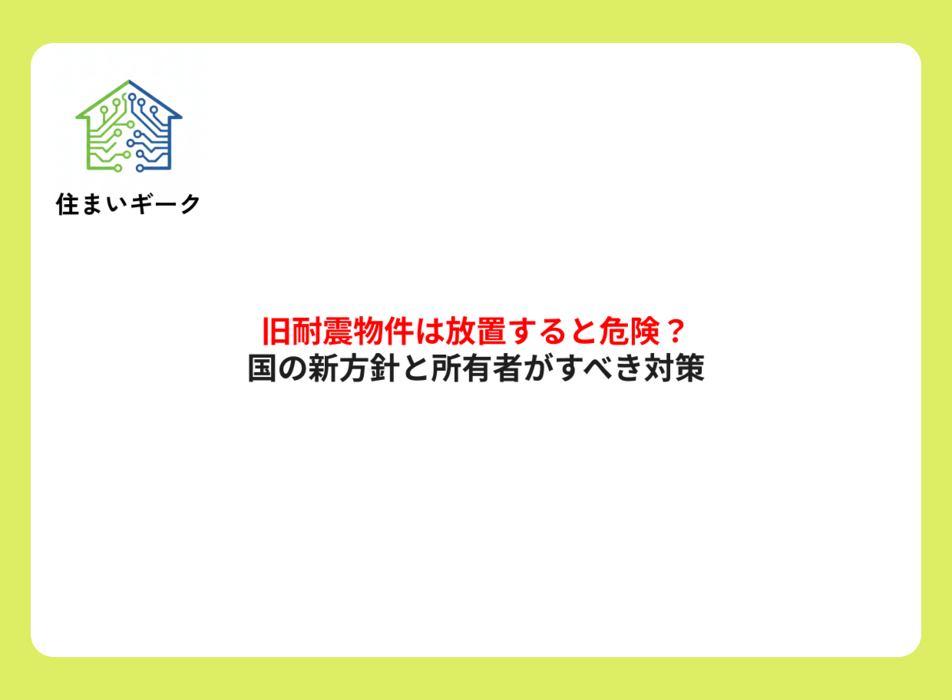所有マンションの資産価値が上がり、大きな含み益が出ている状況は喜ばしいことです。しかし、いざ住み替えを考えると、希望エリアの物件も高騰しており簡単には動けません。含み益は、ただ所有しているだけでは「絵に描いた餅」に過ぎないと感じる方も多いです。この記事では、マンションの含み益がなぜ「取り出せない」と言われるのかを解説します。その上で、住み替えを含めた含み益を現金化・活用するための具体的な方法を提示します。
1. マンションの含み益が「取り出せない」と言われる理由
マンションの含み益を住み替えによって現金化するのが難しい理由は主に2つあります。それは、住み替え先の物件価格も高騰していることと、売却時に諸費用や税金がかかることです。この2つの要因が、手元に残る現金を想定以上に少なくさせてしまいます。
1-1. 住み替え先の物件価格も同時に高騰しているため
所有マンションの価格が上昇している時期は、社会全体の不動産市況が活況なことが多いです。そのため、当然ながら次に購入を検討するマンションの価格も同様に上がっています。結果として、売却で得た利益の多くが、次の物件の購入資金に消えてしまうのです。
例えば、12年前に5,000万円で購入したマンションが8,000万円で売れたとします。住宅ローン残債が2,500万円の場合、単純計算で手元には5,500万円が残る計算です。しかし、同等のエリアや広さで新しいマンションを探すと、価格が9,000万円だったとします。この場合、手元の5,500万円に加えて3,500万円の新たなローンが必要となります。
現在のローン残債2,500万円よりも借入額が増え、月々の返済負担は重くなります。このように、売却額が大きくても購入額も大きくなるため、含み益を現金として取り出すどころか、むしろ追加の資金が必要になるケースが少なくありません。
1-2. 売却時にかかる諸費用や税金が想定以上にかかるため
マンションの売却時には、様々な諸費用や税金が発生することも大きな要因となります。これらのコストは売却価格から差し引かれるため、手元に残る金額を減少させます。主な費用として、不動産会社に支払う仲介手数料が挙げられます。
仲介手数料は売買価格に応じて上限が法律で定められており、8,000万円の物件なら約270万円にもなります。その他にも、売買契約書に貼る印紙税や、住宅ローンを完済するための抵当権抹消登記費用などがかかります。これらの諸費用だけで、売却価格の4%~6%程度が必要になると言われています。
さらに、売却によって利益(譲渡所得)が出た場合は、譲渡所得税と住民税が課されます。利益が大きくなるほど税額も大きくなるため、含み益のすべてが現金として残るわけではありません。これらのコストを考慮せずに資金計画を立てると、想定外の出費に繋がります。
2. マンションの含み益を取り出す4つの具体的な方法
含み益を有効活用する方法は、住み替えだけではありません。現在の家に住み続けながら資金を確保する方法など、ライフプランに合わせた複数の選択肢が存在します。ここでは、代表的な4つの方法について、その仕組みを解説します。
2-1. 方法1:住み替え(エリアや広さの条件を見直す)
含み益を取り出す最も一般的な方法が住み替えです。前述の通り、同条件の物件への住み替えでは現金を残すことは難しい傾向にあります。しかし、住み替え先のエリアを郊外へ移したり、物件の広さや築年数などの条件を見直したりすることで、売却益を手元に残すことが可能になります。
例えば、都心部のマンションを売却し、少し離れた郊外の同程度の広さの新築や中古マンションを購入するケースです。あるいは、子供が独立したタイミングで、よりコンパクトなマンションに住み替える「ダウンサイジング」も有効な選択肢となります。ライフステージの変化に合わせて住環境の条件を柔軟に変更することが、含み-益を現金化する鍵です。
2-2. 方法2:リバースモーゲージ(自宅を担保に老後資金を借入)
リバースモーゲージは、自宅を担保にして金融機関から融資を受ける仕組みの商品です。契約者が生存中は利息のみを返済し、元金は契約者が亡くなった後に自宅を売却するなどして一括で返済します。主に高齢者向けのローンであり、老後の生活資金を確保する目的で利用されます。
この方法の大きな特徴は、今の家に住み続けながら老後資金を得られる点にあります。融資された資金は年金形式で定期的に受け取るか、一括で受け取るかを選べます。ただし、利用には年齢制限(主に55歳や60歳以上)があるほか、対象となる不動産の条件も金融機関によって定められているため、誰でも利用できるわけではありません。
2-3. 方法3:不動産担保ローン(自宅を担保に多目的資金を借入)
不動産担保ローンも、リバースモーゲージと同様に自宅を担保に融資を受ける方法です。しかし、リバースモーゲージが主に老後資金を目的とするのに対し、不動産担保ローンは資金の使い道がより自由であることが特徴です。子供の教育資金や事業資金、リフォーム費用など様々な目的に活用できます。
このローンは無担保ローンに比べて金利が低く、高額な借入が可能な点がメリットです。借入後は、元金と利息を毎月返済していくことになります。住宅ローンが残っている場合でも、含み益の部分を評価して融資を受けられる場合があります。ただし、返済が滞った場合は担保である自宅を失うリスクが伴います。
2-4. 方法4:リースバック(売却後に賃貸として住み続ける)
リースバックは、所有するマンションを不動産会社などに一旦売却し、その後、買主と賃貸借契約を結んでそのまま住み続ける仕組みです。自宅を売却することでまとまった現金を一括で得ながら、住み慣れた環境を変える必要がない点が最大のメリットと言えます。
売却によって所有権が移るため、固定資産税の負担がなくなります。また、将来的にその物件を買い戻すことができる「買戻し特約」を付けられる場合もあります。ただし、売却価格は一般的な市場価格よりも低くなる傾向があり、毎月の家賃負担が発生します。また、賃貸契約には期間が定められているため、永続的に住み続けられる保証はありません。
3. 【徹底比較】含み益を取り出す各方法のメリット・デメリット
4つの方法にはそれぞれ異なる特徴があり、メリットとデメリットが存在します。自身のライフプランや資金ニーズに合わせて、最適な方法を慎重に検討することが重要です。ここでは、各方法の詳細を比較し、どのような人に向いているかを解説します。
3-1. 「住み替え」のメリット・デメリットと向いている人
メリット
* ライフプランの変化に合わせた最適な住環境を実現できます。
* エリアや広さなどの条件次第では、まとまった現金が手元に残ります。
* 新しい設備や間取りの住居で、より快適な生活を始められます。
デメリット
* 住み替え先の物件価格も高騰しているため、持ち出しになる可能性があります。
* 売却と購入のタイミングを合わせるのが難しく、仮住まいが必要になる場合があります。
* 仲介手数料や税金、引越し費用など、諸費用が高額になる傾向があります。
こんな人におすすめ
* 郊外への転居や、家の小型化(ダウンサイジング)を許容できる人。
* 子供の進学や転勤など、明確な理由で住環境の変更が必要な人。
3-2. 「リバースモーゲージ」のメリット・デメリットと向いている人
メリット
* 現在の家に住み続けながら、老後の生活資金を確保できます。
* 毎月の返済は利息のみが基本で、元金返済の負担がありません。
* 相続人に負債が残らない「ノンリコース型」の商品も存在します。
デメリット
* 利用には年齢や物件、エリアなどの厳しい条件が設けられています。
* 金利上昇リスクや不動産価格の下落リスクがあり、借入限度額が変動する可能性があります。
* 原則として、相続人は自宅を相続することができなくなります。
こんな人におすすめ
* 年金収入だけでは老後の生活に不安がある高齢者世帯。
* 自宅を相続させる予定のない人。
3-3. 「不動産担保ローン」のメリット・デメリットと向いている人
メリット
* 今の家に住み続けながら、まとまった資金を調達できます。
* 教育資金や事業資金など、資金の使い道が比較的自由です。
* 無担保ローンと比較して、低金利で高額な借入が可能です。
デメリット
* 毎月の元金と利息の返済義務が発生し、家計を圧迫する可能性があります。
* 返済が困難になった場合、担保である自宅を失うリスクを伴います。
* 事務手数料や保証料、登記費用などの諸費用がかかります。
こんな人におすすめ
* 教育資金や家のリフォームなど、一時的にまとまった資金が必要な人。
* 安定した収入があり、計画的な返済が可能な人。
3-4. 「リースバック」のメリット・デメリットと向いている人
メリット
* 売却によってまとまった現金を一括で得ることができます。
* 引越しが不要で、住み慣れた家にそのまま住み続けられます。
* 所有権が移るため、固定資産税やマンション管理費の負担がなくなります。
デメリット
* 売却価格が、通常の市場価格の7割~9割程度になることが一般的です。
* 所有者ではなくなるため、毎月の家賃が発生します。
* 賃貸契約が更新されず、退去を求められるリスクがあります。
こんな人におすすめ
* 住宅ローンの返済が困難だが、今の家に住み続けたい人。
* 事業資金など、早急にまとまった現金が必要な人。
4. 含み益の現金化で注意すべき税金と諸費用
どの方法を選択するにしても、発生するコストを正確に把握しておくことが不可欠です。特に税金は大きな支出となる可能性があるため、事前に仕組みを理解し、対策を検討することが重要です。
4-1. 売却益にかかる譲渡所得税と3,000万円特別控除
マンションを売却して得た利益は「譲渡所得」として所得税と住民税の課税対象です。譲渡所得は「譲渡価額(売却価格)-(取得費+譲渡費用)」で計算されます。取得費とは物件の購入代金や購入時の仲介手数料などです。
この譲渡所得に対して税金がかかりますが、マイホームを売却した場合には「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が適用できる場合があります。この特例は、譲渡所得から最高3,000万円までを控除できる制度です。つまり、売却益が3,000万円以下であれば、譲渡所得税はかかりません。
この特例を受けるには、自分が住んでいる家屋を売ることや、売った年の前年、前々年にこの特例の適用を受けていないことなど、いくつかの条件を満たす必要があります。
出展:国税庁 No.3302 マイホームを売ったときの特例
4-2. 売却や借入時に発生する諸費用
税金以外にも、様々な諸費用が発生します。これらの費用は現金で支払う必要があるため、事前に準備しておくことが大切です。
売却時にかかる主な諸費用
* 仲介手数料:不動産会社に支払う成功報酬
* 印紙税:売買契約書に貼付する印紙代
* 登記費用:抵当権抹消登記などにかかる登録免許税と司法書士報酬
* 住宅ローン一括返済手数料:金融機関に支払う手数料
借入時(不動産担保ローン等)にかかる主な諸費用
* 事務手数料:金融機関に支払う手数料
* 保証料:保証会社に支払う費用
* 印紙税:金銭消費貸借契約書に貼付する印紙代
* 登記費用:抵当権設定登記にかかる登録免許税と司法書士報酬
5. まとめ:最適な選択は自宅の正確な価値把握から
マンションの含み益は、住み替え先の価格高騰などを理由に「取り出せない」と感じがちです。しかし、実際には住み替えの条件を見直す、あるいはリバースモーゲージや不動産担保ローン、リースバックといった多様な選択肢が存在します。どの方法が最適かは、個々の年齢や家族構成、資金ニーズによって異なります。
重要なのは、含み益という資産を自身のライフプランに合わせてどう活用するかです。その第一歩として、まずは所有するマンションの現在の正確な資産価値を把握することが不可欠です。不動産会社に査定を依頼し、住宅ローン残債を差し引いて、純粋な資産額を明らかにしましょう。
その上で、この記事で紹介した各方法のメリット・デメリットを比較検討し、専門家にも相談しながら、ご自身の状況に最も適した選択をすることが、将来の安心に繋がります。