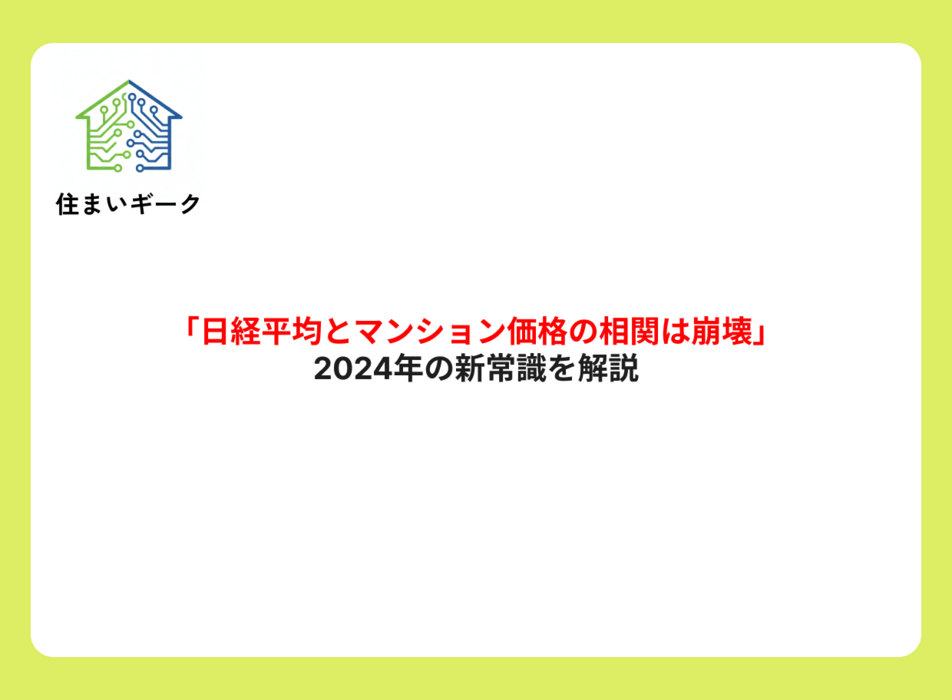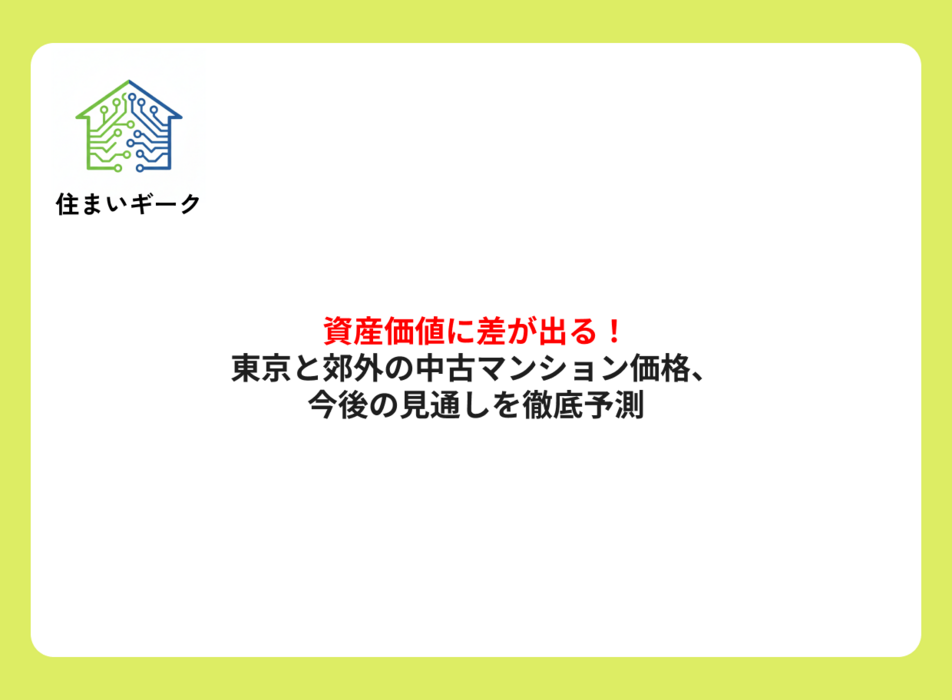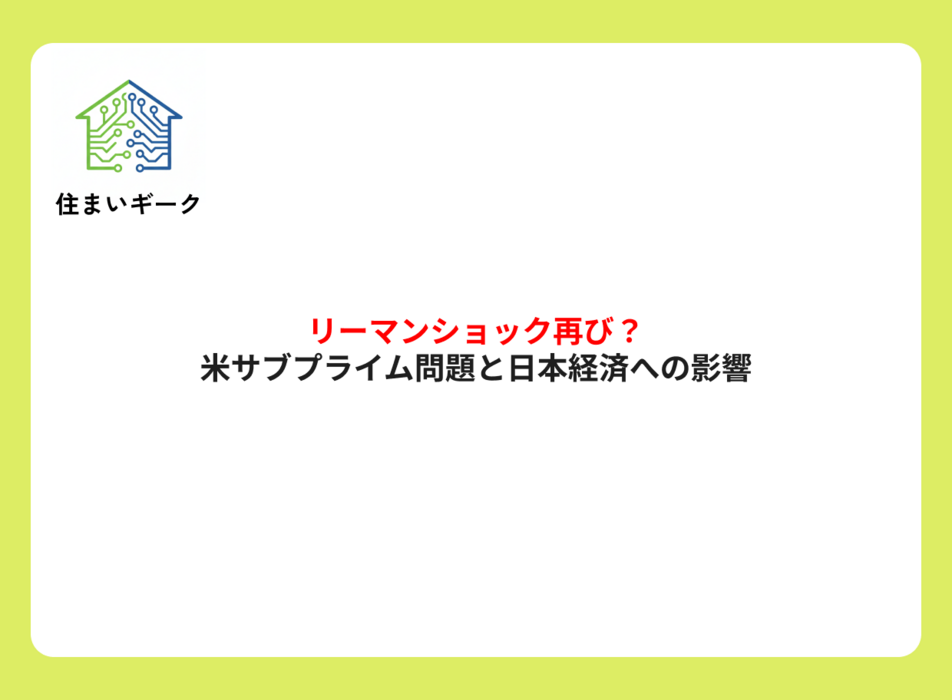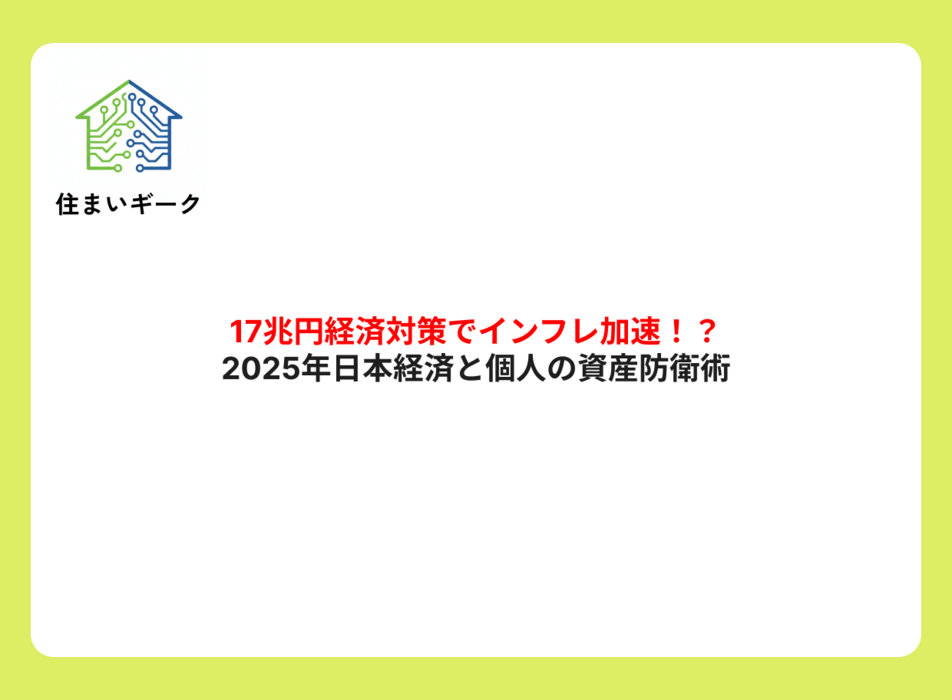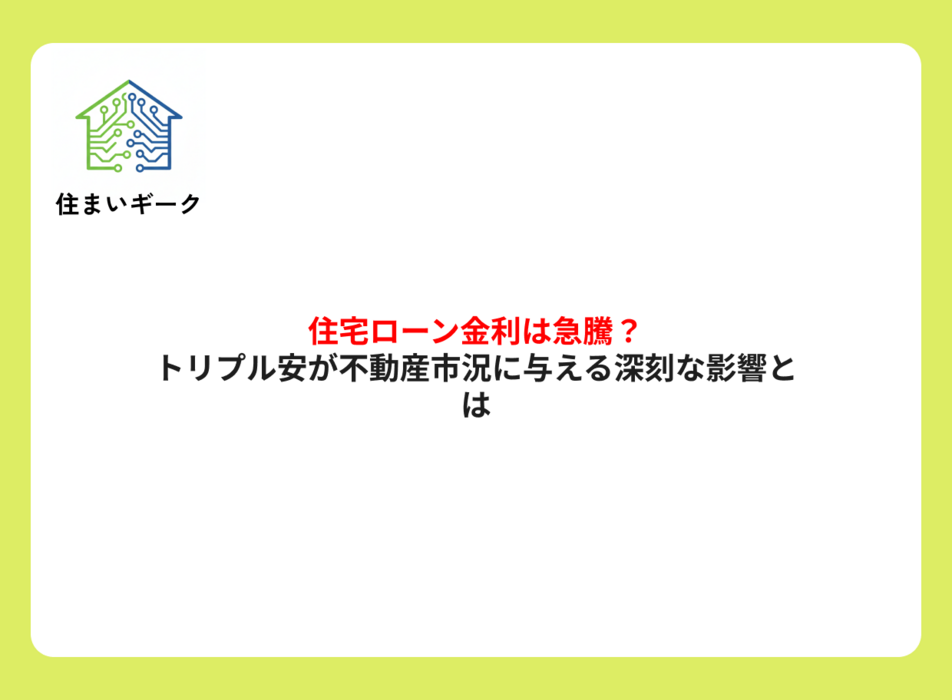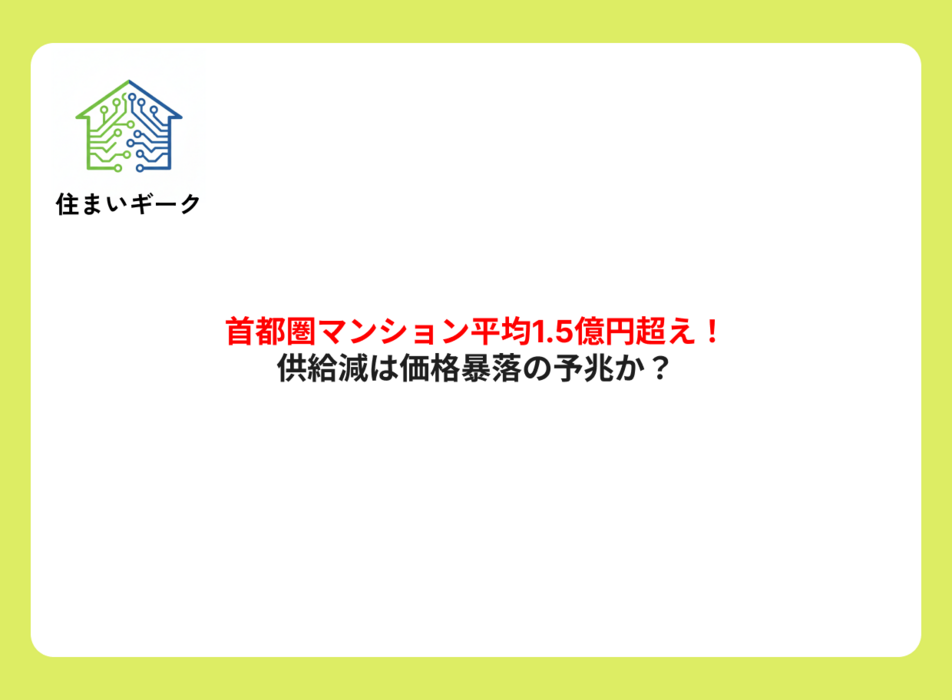1. 「日経平均とマンション価格の相関」通説を紐解く
日経平均株価が史上最高値を更新する中、不動産市場への関心も高まっています。
特に、日経平均株価と東京都の中古マンション価格には強い相関があるという説が、投資家や不動産購入検討者の間で広く共有されてきました。
この通説は、過去のデータに基づいた一定の合理性を持ち、多くの市場関係者が参考にしてきた指標の一つです。
本章では、まずこの相関関係の通説がどのようなものか、そしてなぜそのように考えられてきたのかについて詳しく解説します。
1-1. SNSで語られる「強い相関関係」とは
近年、SNS上では株価とマンション価格の連動性について活発に議論されています。
その中で特に注目されるのが、両者の間に非常に強い正の相関関係が存在するという指摘です。
例えば、「日経平均株価」と「東京の中古マンション価格」の相関係数が0.93に達するという具体的な数値が示されることがあります。
相関係数は1に近いほど二つのデータの関連性が強いことを意味するため、0.93という数値は極めて強い連動性を示唆するものです。
出展: X(旧Twitter) 2024年1月12日の投稿 (https://x.com/mansionDr_TG/status/1745326644158685218)
さらに、この相関関係には時間的なズレがあるとも言われています。
具体的には、中古マンション価格は日経平均株価の変動から約半年遅れて追随する「遅行指標」であるという見方です。
この説に基づけば、日経平均株価が上昇すれば、その約半年後に中古マンション価格も上昇トレンドに入ると予測できることになります。
こうした分かりやすさから、株価の動向をマンション市場の先行指標として捉え、購入や売却のタイミングを計る考え方が広まりました。
出展: X(旧Twitter) 2024年2月22日の投稿 (https://x.com/jun_mansion/status/1966474904196600184)
1-2. 相関関係が生まれる経済的な背景
株価とマンション価格が連動すると考えられてきた背景には、いくつかの経済的なメカニズムが存在します。
最も代表的な要因は、株価上昇がもたらす「資産効果」です。
株価が上昇すると、株式を保有する個人投資家や企業の資産価値が増加し、消費意欲や投資意欲が刺激されます。
特に富裕層や高所得者層においてその効果は顕著であり、増加した資産の一部が高額な不動産の購入に向けられる傾向があります。
この資金流入が、都心部の中古マンション市場の需要を押し上げ、価格上昇に繋がるという構造です。
また、株価は日本経済全体の景況感を反映する代表的な指標です。
日経平均株価が上昇基調にある時期は、企業の業績が好調で、個人の所得や雇用環境も改善に向かうという期待が高まります。
こうした良好なマクロ経済環境は、人々の将来に対する安心感を醸成し、住宅ローンを組んで高額なマンションを購入する決断を後押しします。
つまり、株価とマンション価格は、景況感という共通の要因を介して間接的に連動していると説明できます。
さらに、金融政策も両市場に共通の影響を与える重要な要素です。
例えば、大規模な金融緩和が実施されると、市場に供給される資金量が増加し、金利が低下します。
低金利は企業の資金調達コストを下げて株価を押し上げる一方で、住宅ローン金利の低下を通じて個人の不動産購入を促進します。
このように、金融環境という土台が両市場の価格動向に同じ方向性の影響を与えるため、結果として相関関係が観測されやすくなります。
2. 相関関係に生じた異変と2023年以降の市場動向
長年にわたり市場の経験則とされてきた株価とマンション価格の相関関係ですが、近年その関係性に大きな変化が見られます。
特にコロナ禍を経て、これまでの常識が通用しない新たな局面を迎えているとの指摘が専門家からなされています。
2023年以降のデータは、かつて見られた強い連動性が失われ、両市場がそれぞれ独自の要因で動いている可能性を示唆しています。
ここでは、その具体的な変化の内容と、なぜそのような異変が生じたのか、その背景にある要因を分析します。
2-1. データが示す「相関関係の崩壊」
過去のデータでは確認できた正の相関は、近年著しく弱まっています。
日本経済新聞が2024年9月に発表した分析記事は、この変化を明確に示しています。
同記事によると、リーマン・ショック前からコロナ禍前にかけての期間では、株価とマンション価格には中程度の正の相関が確認されました。
しかし、コロナ禍以降はその相関が弱まり始め、特に2023年以降はほとんど相関が見られなくなったと結論付けています。
出展: 日本経済新聞 2024年9月5日「マンション価格と株価、相関に異変 低い金利が支え」
さらに深刻なのは、単に相関が弱まっただけでなく、関係性が逆転している可能性が示されている点です。
同記事は、分析期間を短くして2019年以降の12カ月の相関を追跡した結果を報告しています。
それによると、2022年までは中程度の相関が維持されていたものの、2023年以降は「弱い負の相関」から「中程度の負の相関」に変化したとのことです。
負の相関とは、一方が上昇するともう一方が下落する傾向があることを意味し、これは従来の通説とは全く逆の動きです。
このデータは、株価上昇が必ずしもマンション価格上昇に繋がらない、新しい市場環境への移行を強く示唆しています。
2-2. なぜ相関は崩れたのか?その要因を分析する
2023年以降に相関関係が崩れた背景には、複数の要因が複雑に絡み合っています。
第一に、マンション価格を直接的に押し上げる固有の要因が強まったことが挙げられます。
その代表例が、深刻な建築コストの高騰です。
ウクライナ情勢や円安を背景とした資材価格の上昇、そして建設業界の人手不足による人件費の増加が新築マンションの価格を押し上げました。
この新築価格の上昇が、相対的に割安な中古マンション市場へ需要をシフトさせ、中古価格も連動して上昇する結果を招いています。
この動きは、株価の動向とは直接関係なく発生する、不動産市場に固有の構造的な問題です。
第二に、海外投資家の存在感が増していることも大きな要因です。
長期的な円安トレンドは、海外の投資家から見ると日本の不動産が割安に映る状況を生み出しました。
特に政治的に安定し、高い利回りが期待できる東京の不動産は、海外の富裕層や機関投資家にとって魅力的な投資対象となっています。
彼らの旺盛な購入意欲が、国内の景況感や株価の動向とは独立した形でマンション価格を支え、あるいは押し上げる力として作用しています。
第三に、国内の金融環境が依然として緩和的であることも見逃せません。
欧米の中央銀行がインフレ抑制のために利上げを進める中でも、日本銀行は金融緩和政策を長期間維持してきました。
これにより、住宅ローン金利は歴史的な低水準で推移し続けており、高騰するマンション価格にもかかわらず、購入者の負担を軽減する効果を果たしています。
この極めて低い金利環境が、株価の変動とは別のロジックで不動産市場の底堅い需要を支え、相関関係を弱める一因となっていると考えられます。
3. 現在の市場環境から読み解く今後のマンション価格
株価との相関が崩れた今、今後のマンション価格の動向を予測するためには、より多角的な視点が必要不可欠です。
過去の経験則であった「株価が上がればマンション価格も上がる」という単純な図式は、もはや有効ではない可能性が高いと言えます。
金利の動向、需給バランス、そして国内外の投資家の動きなど、不動産市場に特有の要因を個別に分析し、総合的に判断することが求められます。
ここでは、現在の市場環境を形成する主要な要因を整理し、それらが今後の価格推移に与える影響について考察します。
3-1. 株価以外に注目すべき価格決定要因
今後のマンション価格を占う上で、最も重要な変数の一つが金融政策と金利の動向です。
現在、住宅ローン金利は依然として低位で安定していますが、日本銀行がマイナス金利政策を解除したことで、将来的な金利上昇への警戒感が生まれています。
変動金利型の住宅ローンを利用している層が多い中、将来的な金利上昇は返済額の増加に直結し、家計を圧迫する可能性があります。
これにより、新規の購入需要が減退したり、返済困難な物件が市場に放出されたりすれば、価格の下落圧力となることも考えられます。
次に、市場の需給バランスも価格を左右する基本的な要因です。
特に東京都心部では、新規にマンションを建設できる用地が限られており、供給戸数が伸び悩む傾向にあります。
一方で、共働き世帯(パワーカップル)の増加や、相続税対策を目的とした富裕層の購入意欲は依然として旺盛です。
このように、限られた供給に対して根強い需要が存在する限り、価格は高止まりしやすい地合いが続くと考えられます。
エリアや物件の特性によって需給バランスは異なるため、マクロな動向だけでなく、ミクロな視点での分析も重要になります。
さらに、インフレと人々の所得動向も無視できない要素です。
物価上昇が続く中で、実質的な賃金がそれに追いついていない状況は、一般層の住宅購入能力を低下させます。
高額なマンションを購入できる層が一部の富裕層や高所得者に限定されていくと、市場全体の勢いが失われる可能性があります。
今後の春闘などにおける賃上げの動向が、住宅市場の持続性を判断する上での一つの試金石となるでしょう。
3-2. 今後の価格推移に関する冷静な考察
これらの要因を総合的に考慮すると、今後のマンション価格の推移を一概に予測することは極めて困難です。
日経平均株価が堅調に推移したとしても、それが直接的にマンション価格の上昇に結びつくとは断定できません。
むしろ、金利の上昇リスクや、一般層の購買力低下といった下落要因と、都心部の供給不足や海外からの資金流入といった上昇要因が綱引きする展開が予想されます。
結果として、市場の二極化がさらに進む可能性が考えられます。
交通利便性や生活環境に優れた都心・駅近の優良物件は、国内外の旺盛な需要に支えられて高値を維持、あるいは上昇を続けるかもしれません。
一方で、郊外や駅から離れた物件、築年数が経過した物件などは、金利上昇や需要減退の影響を受けやすく、価格が調整局面に入る可能性があります。
「マンション」という大きな括りではなく、立地や物件の個別性を精査する視点がこれまで以上に重要になります。
したがって、不動産の購入を検討する際には、株価の動向のみに一喜一憂するべきではありません。
自身のライフプランや資金計画に基づき、無理のない返済が可能な範囲で物件を選ぶことが基本です。
その上で、金利や税制、都市開発計画といった不動産市場固有の情報を多角的に収集し、冷静に判断することが求められます。
4. まとめ:不動産購入における新たな視点の必要性
本稿では、日経平均株価と中古マンション価格の相関関係について、その通説と近年の変化を分析しました。
かつては強い正の相関が見られ、株価はマンション市場の先行指標と見なされてきましたが、その関係性は2023年以降、大きく変化しています。
日本経済新聞の分析によれば、近年は相関がほぼ見られず、むしろ負の相関に転じている可能性さえ指摘されています。
この背景には、建築費の高騰や海外投資家の流入、継続的な金融緩和など、不動産市場に固有の要因が強く影響していると考えられます。
この変化は、私たちが不動産市場を分析し、将来を予測する上での視点を根本的に見直す必要があることを示唆しています。
株価という単一の指標に依存した短期的な価格予測は、もはや現実的ではありません。
これからの不動産購入検討者には、金利動向、需給バランス、都市計画、そして物件の個別性といった複数の要因を総合的に評価する、より緻密で冷静なアプローチが求められます。
過去の経験則が通用しなくなった現代において、安易な情報に流されることなく、多角的な情報収集に基づいた自己判断こそが、長期的に価値のある資産形成に繋がる唯一の道と言えるでしょう。