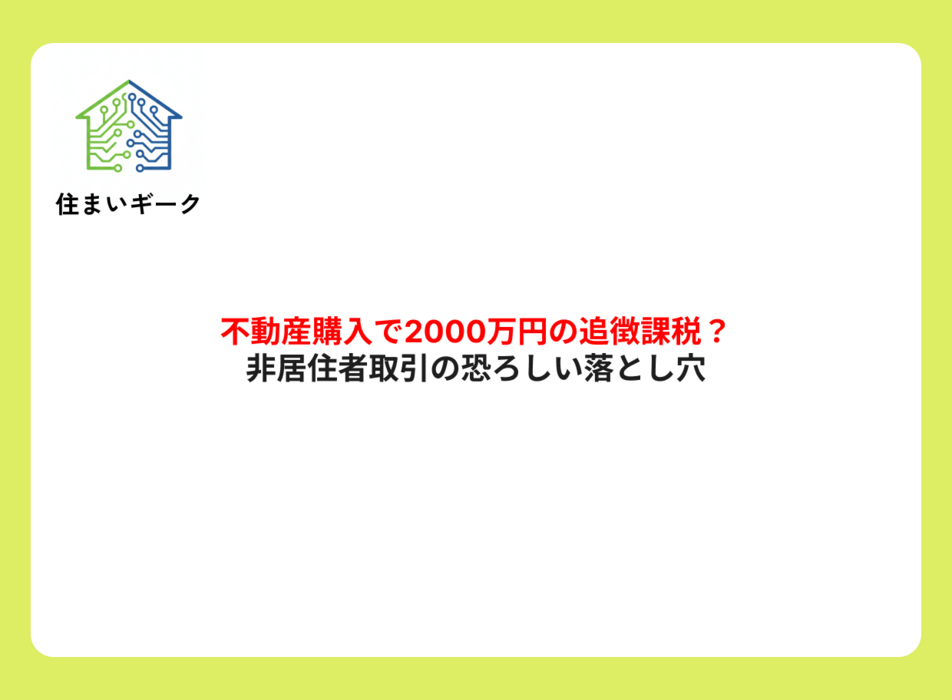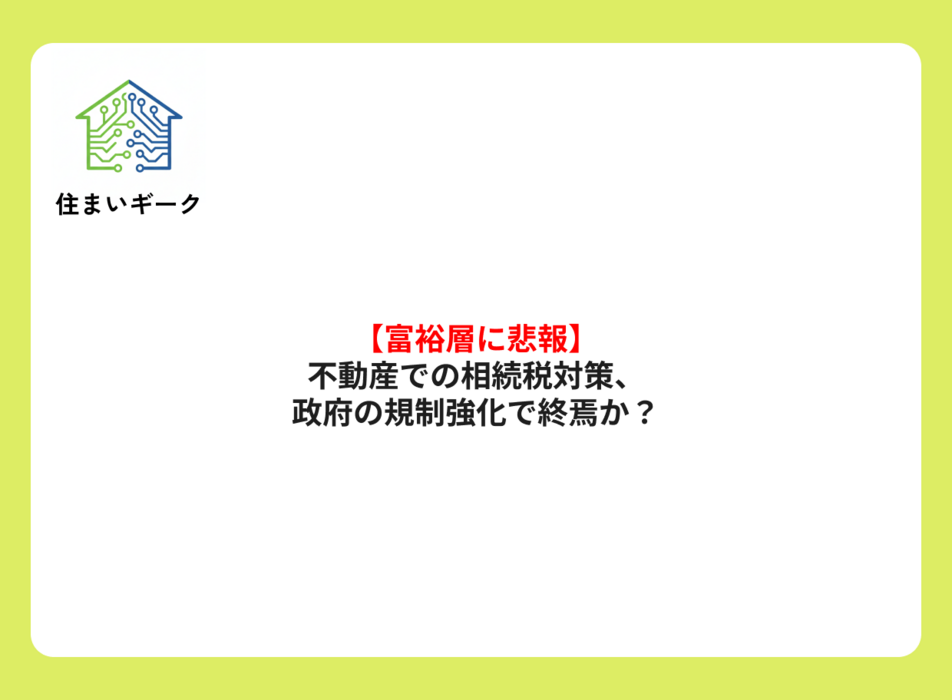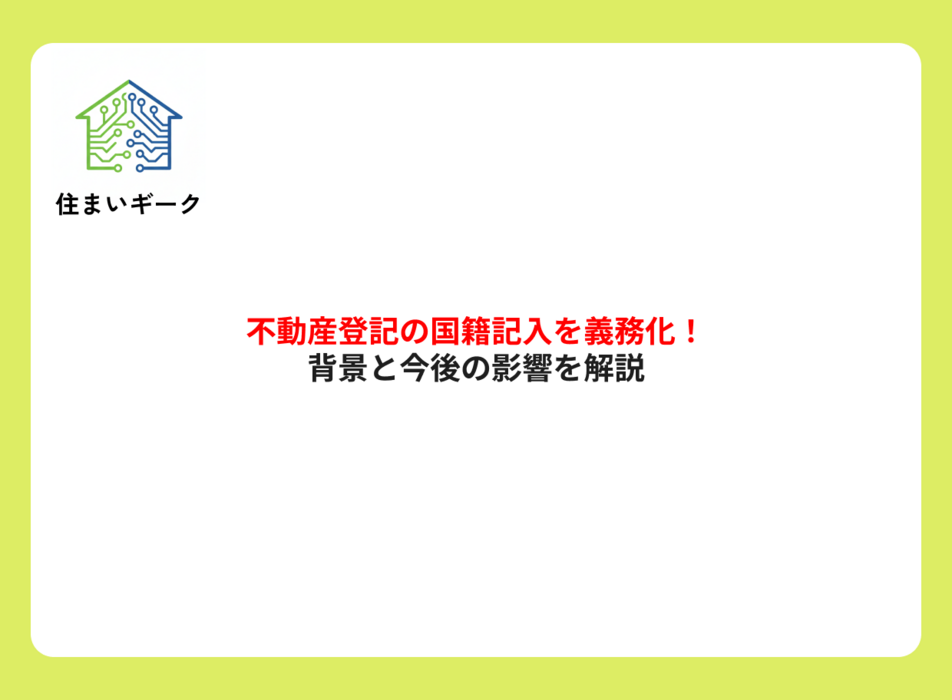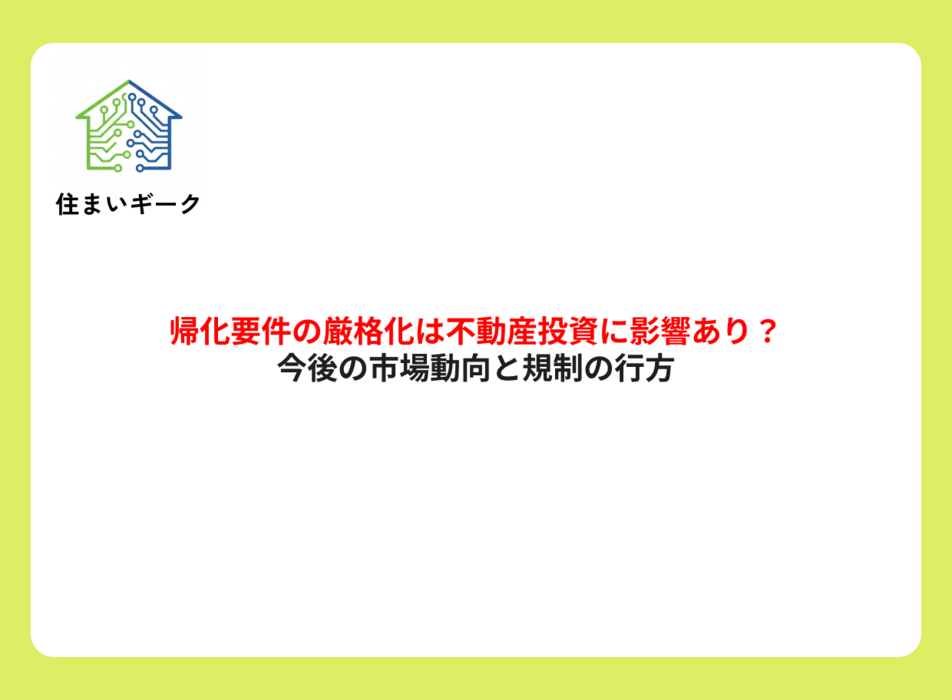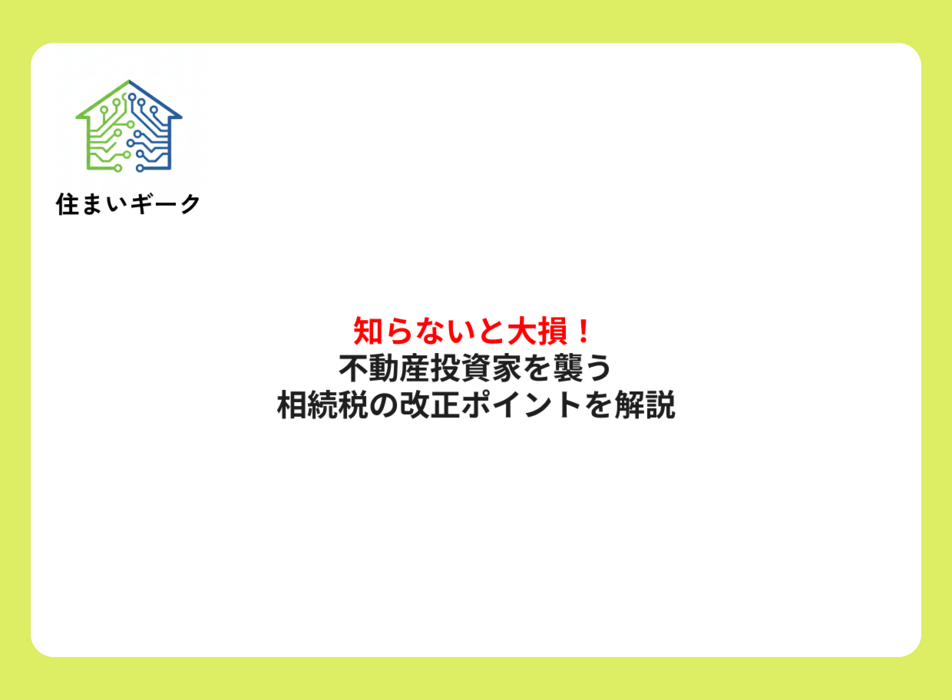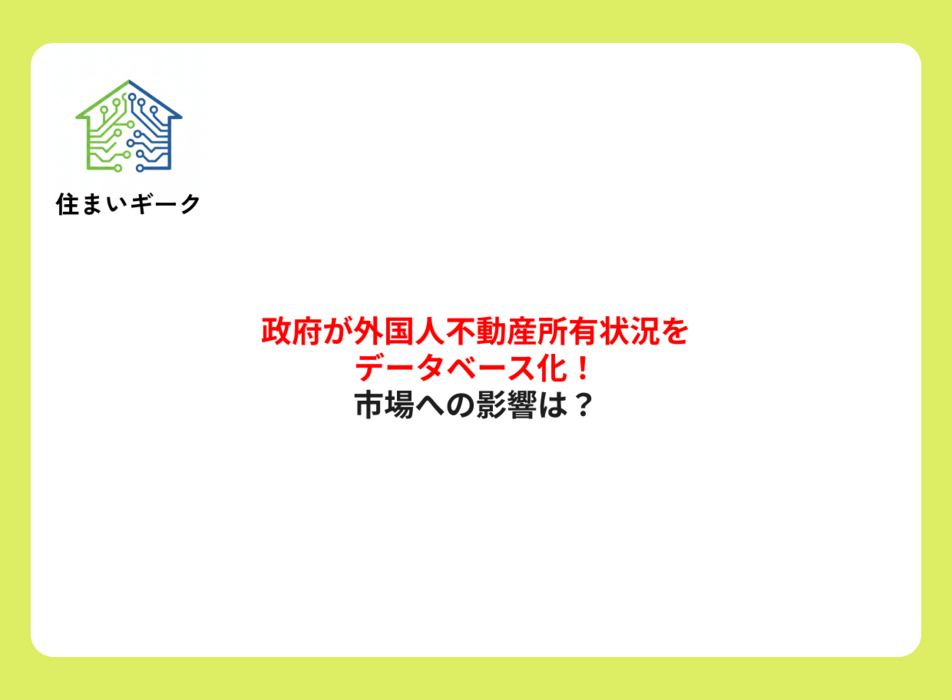1. SNSで話題の不動産取引トラブル、その深刻な実態
近年の不動産市場の活況とともに、これまであまり知られていなかった取引上のリスクが表面化しつつあります。特に、海外に居住する個人、いわゆる「非居住者」から不動産を購入する際に発生する税務上の問題は、買主にとって深刻な金銭的負担となりかねないため、正確な知識を持つことが不可欠です。本記事では、SNSで注目された事例を基に、その制度の詳細と買主が講じるべき具体的な対応策を網羅的に解説します。
1-1. 2,000万円の追徴課税、個人に降りかかった突然の納税義務
2025年11月21日、あるX(旧ツイッター)ユーザーの投稿が不動産取引に関心を持つ人々の間で大きな注目を集めました。その内容は、外国人(非居住者)からタワーマンションを購入した際、本来は売主が納めるべき税金を源泉徴収しなかったため、税務署から徴収漏れを指摘され、買主自身が合計で2,000万円以上を納税することになったという衝撃的なものでした。この投稿は、多くの人にとって寝耳に水ともいえる税務上の義務の存在を浮き彫りにしました。
この事象の根幹にあるのは、日本の所得税法に定められた「非居住者等からの土地等の譲受け人の源泉徴収義務」という制度です。この制度は、非居住者が日本国内の不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対する税金を確実に徴収することを目的としています。売主が海外にいる場合、日本での確定申告や納税が適切に行われない可能性があるため、その徴収を担保する目的で、買主側に税金を天引きして国に納付する義務が課されているのです。
投稿者はこの義務を知らずに取引を完了させ、売買代金の全額を売主に支払ってしまいました。その後、税務署からの指摘により、本来売主が負担すべきであった譲渡所得税相当額を、買主が代わりに納付するよう求められたと考えられます。2,000万円という金額は、取引額がいかに高額であったかを物語っており、個人が突然負担するには極めて大きな金額と言えるでしょう。この事例は、決して他人事ではなく、非居住者との不動産取引を行うすべての買主に警鐘を鳴らすものとなっています。
1-2. 「不動産契約のバグ」と呼ばれる制度上の落とし穴とは
前述の投稿者は、この源泉徴収義務を「不動産契約の危険なバグ」と表現しています。この表現が的を射ている点は、この重要な義務が、宅地建物取引業法で定められた「重要事項説明」の対象項目に含まれていないという事実にあります。重要事項説明とは、不動産取引において買主が不利益を被ることがないよう、宅地建物取引士が契約前に物件や取引条件に関する重要な情報を説明するものです。
しかし、売主が非居住者である場合の源泉徴収義務については、重要事項説明の法的義務の範囲外とされています。そのため、不動産仲介業者がこの制度に精通していなかったり、あるいは意図的に説明を省略したりした場合、買主はリスクを全く認識しないまま契約を進めてしまう可能性があります。買主が善意であったとしても、納税義務を免れることはできません。法律上、納税義務の主体はあくまで買主本人とされているため、「知らなかった」という言い分は通用しないのです。
これが「バグ」と称される所以であり、不動産取引という高額な契約において、買主が自己防衛のために能動的に情報を収集し、確認する必要があるという厳しい現実を示唆しています。特に、住宅ローンを利用して不動産を購入する一般の個人買主にとっては、予定外の納税資金を捻出することは極めて困難であり、生活設計そのものを揺るがしかねない深刻な事態に発展する危険性をはらんでいます。
2. 知らないでは済まされない「非居住者からの不動産購入と源泉徴収」
この源泉徴収義務は、不動産取引における買主の責任を定めた重要な法律です。制度の目的や具体的な条件、手続きを正しく理解することは、予期せぬ金銭的負担を回避するための第一歩となります。ここでは、制度の核心部分をより詳細に、そして分かりやすく解説していきます。専門的な内容も含まれますが、安全な取引を実現するためには不可欠な知識です。
2-1. なぜ買主が売主の税金を払うのか?制度の目的と背景
買主が売主の税金を代わりに納めるという仕組みは、一見すると不合理に感じられるかもしれません。しかし、これには明確な税務上の理由が存在します。日本の税法では、国内にある不動産の売却によって生じた所得(譲渡所得)は、たとえ売主が海外に住む非居住者であっても、日本の所得税の課税対象となります。これを「源泉地国課税の原則」と呼びます。
問題は、その税金をいかにして確実に徴収するかという点です。売主が非居住者である場合、日本国内に住所や事業所を持たないことが多く、売却代金を受け取った後にそのまま海外へ送金してしまうと、日本の税務当局がその所得を捕捉し、税金を徴収することが極めて困難になります。申告漏れや納税に至らないケースが多発する懸念があるため、国は徴収の確実性を高めるための特別な仕組みを設けました。
それが、源泉徴収制度です。所得の支払者、この場合は不動産の買主に、代金を支払う段階で税金分をあらかじめ天引きさせ、国に納付させることで、徴収漏れのリスクを大幅に軽減しています。つまり、買主は納税義務者である売主に代わって、納税手続きの一部を代行する役割を法的に負わされているのです。この制度があることにより、非居住者であっても適正な課税が担保される仕組みとなっています。
2-2. 源泉徴収義務が発生する具体的な条件
買主に源泉徴収義務が発生するかどうかは、いくつかの条件によって決まります。すべての非居住者との取引で義務が生じるわけではないため、以下の条件を正確に把握しておくことが重要です。国税庁の指針に基づき、義務が発生する基本的な要件を整理します。
第一の要件は、売主が所得税法上の「非居住者」または「外国法人」であることです。非居住者とは、日本国内に住所を有さず、かつ、現在まで引き続いて1年以上居所を有しない個人を指します。国籍が日本人であっても、生活の本拠が海外にあれば非居住者と判定されるため、「外国人=非居住者」という短絡的な判断は危険です。
第二の要件は、取引の対象が「土地等」であることです。これには、土地や建物はもちろんのこと、土地の上に存する権利(借地権など)も含まれます。一般的な不動産売買は、ほぼこの要件に該当すると考えてよいでしょう。
これらの基本要件を満たした上で、買主が源泉徴収義務を負うことになります。ただし、後述する例外規定に該当する場合は、この義務が免除されます。特に個人が買主となる場合には、この例外規定に当てはまるかどうかの確認が極めて重要です。投資目的での購入や、売買価格が高額な取引では、源泉徴収義務が発生する可能性が高いと認識しておく必要があります。
2-3. 税率10.21%の計算と納税手続きの基本
源泉徴収義務があると判断された場合、買主が徴収すべき税額は、不動産の譲渡対価、つまり売買代金の総額に対して10.21%を乗じて計算します。この税率は、所得税の10%と、その所得税額に対する復興特別所得税2.1%を合わせたものです。例えば、売買価格が2億円の物件であれば、2億円 × 10.21% = 2,042万円を源泉徴収する必要があります。
この計算された税額を、買主は売買代金から差し引いて売主に支払います。そして、差し引いた税金は、代金を支払った月の翌月10日までに、所轄の税務署に納付しなければなりません。納付の際には、「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」という専用の納付書を使用します。この納付書は税務署で入手するか、国税庁のウェブサイトからダウンロードすることも可能です。
手続きの流れをまとめると以下のようになります。
1. 売買契約時に、源泉徴収を行う旨を売主と合意し、契約書に明記する。
2. 売買代金の決済日(残金支払日)に、代金総額から10.21%の税額を差し引いた金額を売主に支払う。
3. 差し引いた源泉徴収税額を、決済日の属する月の翌月10日までに、専用の納付書を用いて金融機関または所轄税務署の窓口で納付する。
この一連の手続きを遅滞なく行うことが、買主の法的な義務となります。
2-4. 義務を怠った場合に買主が負うペナルティ
もし買主が源泉徴収と納税の義務を怠った場合、どうなるのでしょうか。この場合、税務署は源泉徴収義務者である買主に対して、「納税告知」を行います。これは、本来徴収して納付すべきであった税額を、買主自身の責任で納付しなさいという行政処分です。SNSの事例のように、本来売主が負担すべき税金を、買主が自らの資金で立て替えて納付する事態に陥ります。
さらに、ペナルティは本税の納付だけに留まりません。法定の納付期限(代金を支払った月の翌月10日)を過ぎて納税告知を受けた場合、原則として「不納付加算税」が課されます。不納付加算税の税率は、自主的に納付した場合は5%、税務調査による指摘後に納付した場合は10%となります。
加えて、法定納付期限の翌日から実際に納付する日までの日数に応じて、「延滞税」も発生します。延滞税の税率は年によって変動しますが、長期間滞納すればその負担は決して軽視できません。このように、源泉徴収義務の不履行は、本来不要であったはずの加算税や延滞税といった追加的な金銭負担まで招く、非常にリスクの高い行為なのです。
3. 予期せぬ納税を防ぐための完全ガイド
非居住者との不動産取引に潜む源泉徴収のリスクは、正しい知識と手順を踏むことで確実に回避することが可能です。ここでは、買主が自身の資産を守るために実践すべき具体的な自己防衛策を、取引の段階ごとに整理して解説します。これらの対策を講じることで、安心して取引を進めることができるようになります。
3-1. 取引前に必ず確認すべき売主の「居住性」
すべての対策の出発点となるのが、売主が所得税法上の「居住者」か「非居住者」かを見極めることです。この確認を怠ると、その後のすべての判断が誤った前提に基づいて行われることになりかねません。確認は、不動産仲介業者を介して、売主本人に直接行ってもらうのが最も確実な方法です。
具体的には、売主の現在の住所地を確認します。住民票の写しなどを提示してもらい、その住所が日本国内にあるかを確認します。ただし、住民票が国内に残っていても、生活の実態が海外にある場合は非居住者と判断されることがあるため、より慎重な確認が必要です。海外勤務の期間や目的、日本不在期間中の国内資産の管理状況、家族の居住地といった要素を総合的に勘案して判断されます。
買主の立場からは、売主に「非居住者に該当しないことの申告書」といった形式で、居住者であることを書面で確約してもらう方法も有効です。もし売主が非居住者である、またはその可能性があると判明した場合は、直ちに源泉徴収の要否を検討するステップに進む必要があります。この初期段階での確認こそが、後のトラブルを防ぐ最大の鍵となります。
3-2. 源泉徴収が不要になる例外規定を正しく理解する
売主が非居住者であると判明した場合でも、常に源泉徴収が必要になるわけではありません。買主が個人の場合に限り、特定の条件を満たすことで源泉徴収義務が免除される例外規定が存在します。この規定を正しく理解し、自身の取引が該当するかを判断することが重要です。
国税庁によると、源泉徴収が不要となるのは、以下の3つの要件をすべて満たす場合に限られます。
1. 売主が個人であること: 売主が外国法人である場合は、この例外規定の適用はなく、必ず源泉徴収が必要となります。
2. 譲渡対価(売買価格)が1億円以下であること: 消費税が含まれる場合は、消費税込みの金額で判断します。売買価格が1円でも1億円を超えると、この要件を満たさなくなります。
3. 買主が、自己またはその親族の居住の用に供するために購入すること: いわゆるマイホームとしての購入がこれに該当します。投資用物件、別荘、事業用の物件としての購入は対象外となります。
出展: 国税庁 タックスアンサー No.1444「非居住者から土地などを買ったとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2879.htm
この3つの要件は「すべて」満たす必要がある点に注意が必要です。例えば、8,000万円の物件を自己の居住用に購入したとしても、売主が外国法人であれば源泉徴収は必要です。また、個人から5,000万円の物件を購入した場合でも、それが投資用マンションであれば、やはり源泉徴収義務が発生します。自身の購入目的と取引価格を照らし合わせ、この例外規定に該当するかを厳密に確認してください。
3-3. 売買契約書に盛り込むべき重要な特約条項
売主が非居住者であり、かつ例外規定にも該当せず、源泉徴収義務が発生すると判断された場合、その手続きについて売買契約書に明確に記載しておくことが後のトラブルを避ける上で極めて重要です。口頭での確認だけでなく、法的な効力を持つ契約書に明記することで、双方の認識を一致させ、義務の履行を確実にします。
契約書には、以下のような内容を盛り込んだ特約条項を追加することを推奨します。
* 源泉徴収義務の確認: 本取引の売主が所得税法上の非居住者に該当し、買主が所得税法第212条第1項に定める源泉徴収義務を負うことを、売主・買主双方が確認する旨を記載します。
* 源泉徴収税額の明記: 譲渡対価の10.21%に相当する具体的な金額を計算し、その額を源泉徴収する旨を記載します。
* 支払い金額の内訳: 買主は、売買代金から上記の源泉徴収税額を控除した残額を、売主の指定する口座に支払う旨を記載します。
* 納税義務の主体: 買主は、控除した源泉徴収税額を、法令に定められた期限までに責任をもって所轄税務署に納付する旨を記載します。
* 協力義務: 売主は、買主が源泉徴収および納税手続きを円滑に行うために必要な情報提供等に協力する旨を記載します。
これらの条項を盛り込むことで、決済日になってから「代金が全額支払われない」といった売主との間の紛争を防ぎ、買主は法的な根拠をもって手続きを進めることができます。
3-4. 不安を解消する専門家への相談タイミングと費用
非居住者との不動産取引は、税務上の判断が複雑になるケースが多く、少しでも不安や疑問を感じた場合は、速やかに専門家へ相談することが最善の策です。特に、売主の居住性の判断が難しい場合や、契約書の特約条項の作成に自信がない場合は、専門家の知見を活用すべきです。
相談相手としては、国際税務に詳しい税理士が最も適任です。税理士は、具体的な状況をヒアリングした上で、源泉徴収義務の有無を的確に判断し、必要な手続きについて具体的なアドバイスを提供してくれます。また、納税手続きの代行を依頼することも可能です。不動産取引に詳しい弁護士に相談し、契約書の内容をリーガルチェックしてもらうことも有効な手段です。
相談するタイミングは、早ければ早いほど良いですが、遅くとも売買契約を締結する前には行うべきです。契約後に問題が発覚すると、解決が困難になる場合があります。専門家への相談費用は、相談内容や依頼する業務の範囲によって異なりますが、一般的に数万円から十数万円程度が目安となります。しかし、数千万円にもなり得る予期せぬ納税リスクを回避できることを考えれば、これは必要不可欠なコストと言えるでしょう。
4. 非居住者との不動産取引に関するQ&A
ここまで制度の概要と対策について解説してきましたが、実際の取引ではさらに個別具体的な疑問が生じることがあります。このセクションでは、買主の皆様からよく寄せられる質問とその回答をQ&A形式でまとめました。ご自身の状況と照らし合わせながら、理解を深めるための一助としてください。
4-1. 売主が日本人でも「非居住者」に該当しますか?
はい、該当する場合があります。所得税法における「居住者」か「非居住者」かの判定は、国籍ではなく、生活の本拠である「住所」が日本国内にあるかどうかで判断されます。例えば、海外の企業に勤務しており、家族と共に海外で生活している日本人は、たとえ日本の国籍を持っていても税法上は「非居住者」として扱われます。したがって、売主が日本人であるという理由だけで、源泉徴収が不要だと安易に判断することはできません。取引にあたっては、国籍に関わらず、現在の生活実態がどこにあるのかを必ず確認する必要があります。
4-2. 共有名義の不動産を購入する場合はどうなりますか?
不動産が共有名義であり、共有者の中に非居住者が含まれている場合は、その非居住者の持ち分に相当する譲渡対価に対してのみ源泉徴収義務が発生します。例えば、Aさん(居住者)とBさん(非居住者)がそれぞれ2分の1の持ち分を持つ物件を総額8,000万円で購入する場合を考えます。この場合、買主は非居住者であるBさんの持ち分、すなわち4,000万円に対して10.21%の源泉徴収を行う必要があります。計算すると、4,000万円 × 10.21% = 408万4,000円となります。この額を徴収し、税務署に納付します。居住者であるAさんの持ち分(4,000万円)については源泉徴収の必要はありません。
4-3. 売主が海外法人の場合も源泉徴収は必要ですか?
はい、必要です。売主が外国法人である場合、個人が買主の場合に適用される例外規定(1億円以下のマイホーム購入)は適用されません。したがって、譲渡対価の金額や購入目的を問わず、原則としてすべての取引で譲渡対価の10.21%を源泉徴収し、納付する義務が生じます。企業が所有するリゾート物件や社宅などを個人が購入するケースなどが考えられますが、売主が外国法人であると判明した時点で、源泉徴収は必須の手続きであると認識してください。
4-4. すでに取引が完了し、税務署から通知が来た場合の対処法は?
万が一、源泉徴収義務を知らずに取引を終え、後日税務署から「納税告知書」や「お尋ね」といった書類が届いた場合は、速やかに行動する必要があります。まずは、通知の内容を正確に把握し、記載された納税額や納付期限を確認します。その上で、直ちに税理士などの専門家に相談することを強く推奨します。専門家は、納税告知に対する法的な妥当性を検討し、今後の対応策(分納の交渉など)について助言してくれます。無視や放置は、延滞税が増え続けるだけでなく、最悪の場合、財産の差し押さえといった事態に発展する可能性もあるため、誠実かつ迅速に対応することが何よりも重要です。