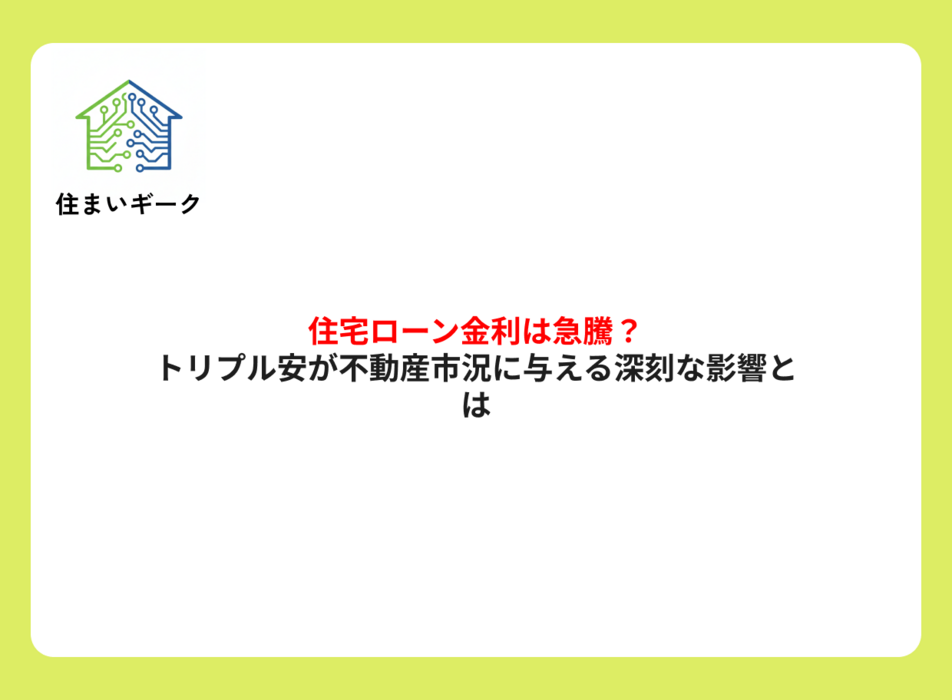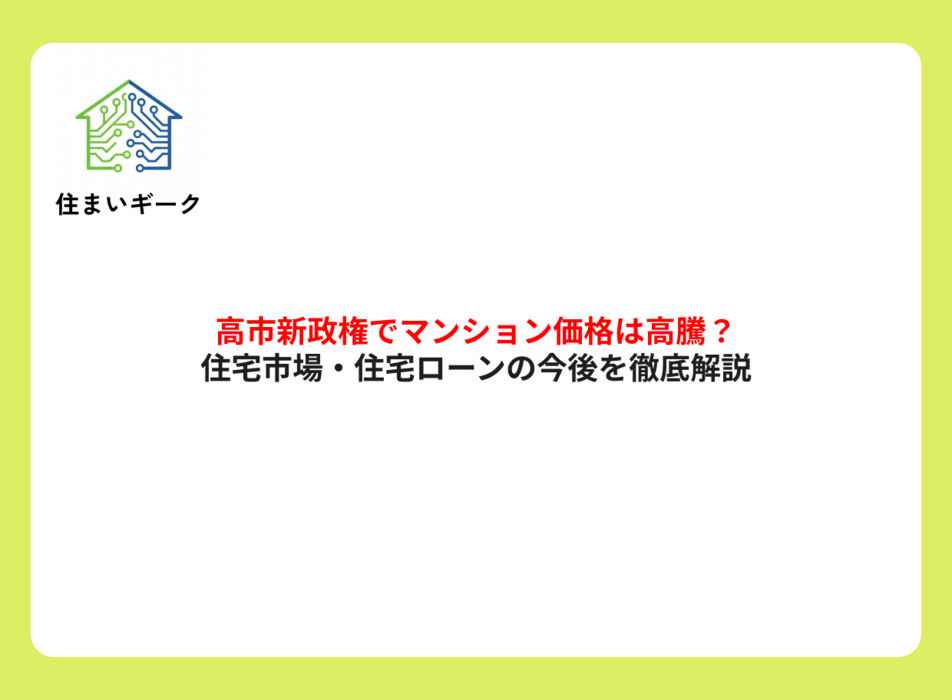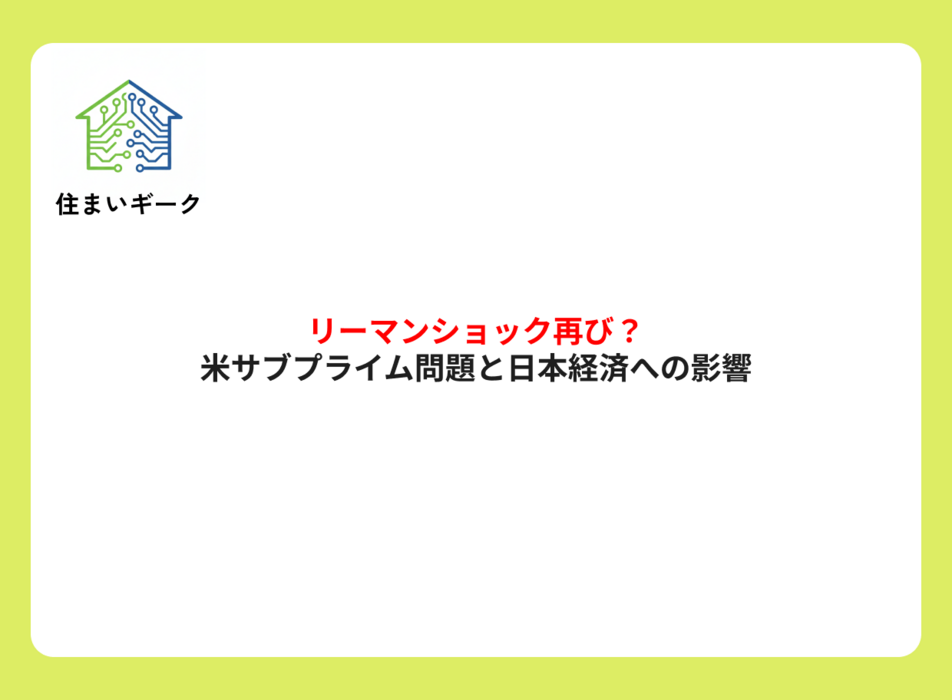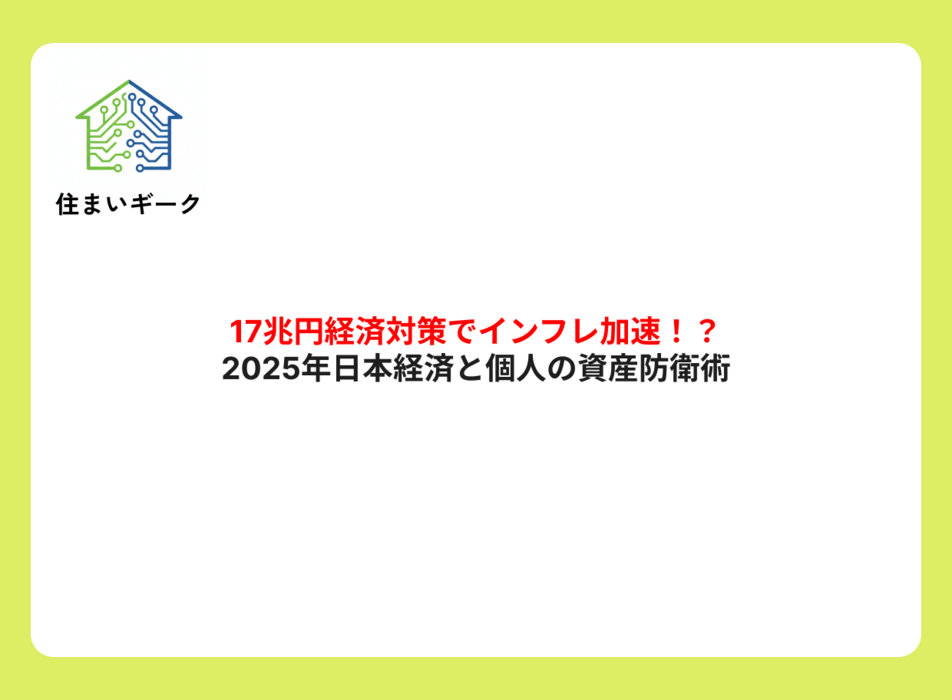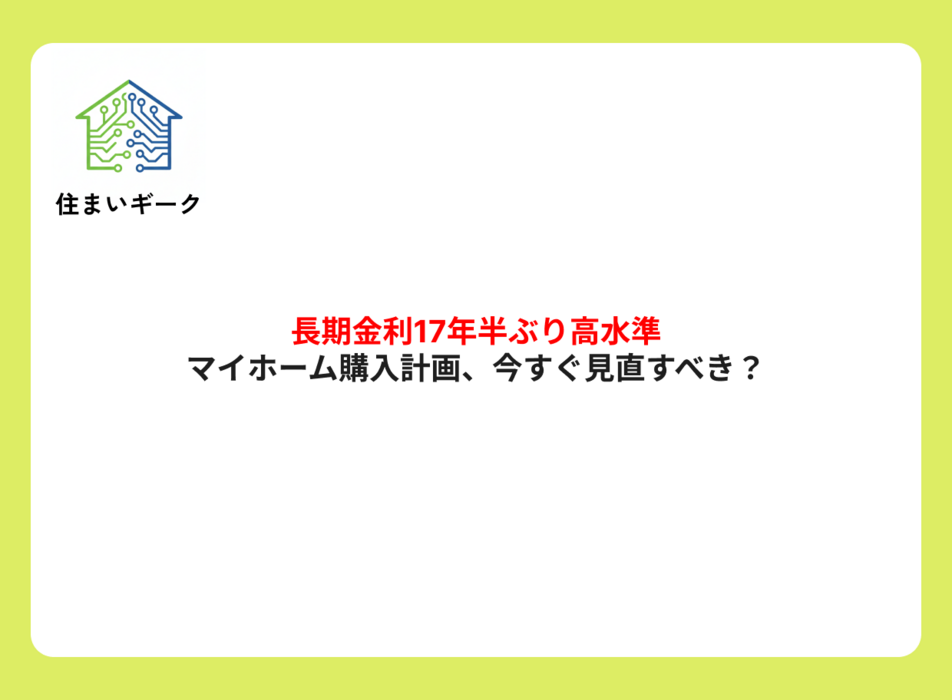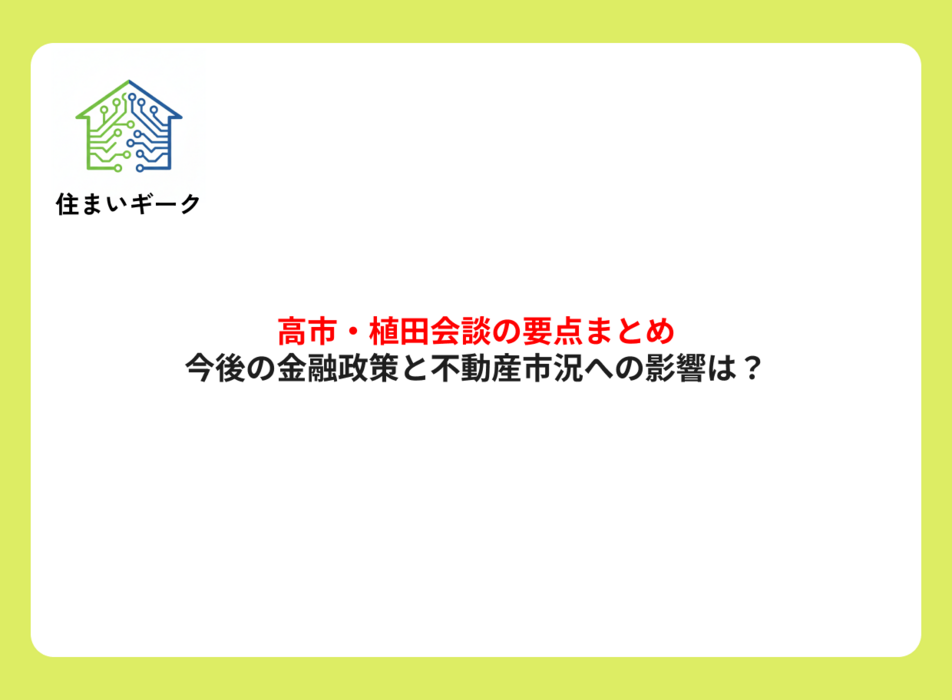1. 高市政権発足後に急浮上した「トリプル安」のリスク
高市首相の就任後、日本経済は新たな期待感とともに幕を開けました。しかし、その期待は短期間で大きな懸念へと変わり始めています。積極的な財政政策への期待から生まれた市場の楽観ムードは一転し、現在では株価、債券、そして円が同時に下落する「トリプル安」への警戒感が急速に高まっている状況です。本章では、市場心理が急変した背景とトリプル安の具体的なメカニズム、そして過去の海外事例との比較を通じて、現状のリスクを多角的に分析します。
1-1. 期待から懸念へ、市場心理の急変
高市政権が発足した当初、市場は積極的な財政・経済政策を好感しました。これらの政策が日本経済の長年の課題であるデフレからの完全脱却を促し、持続的な成長軌道に乗せるという期待が広がったためです。この期待感を背景に、日経平均株価は10月末にかけて史上最高値を更新するなど、いわゆる「高市トレード」と呼ばれる活況を呈していました。投資家たちは、大胆な景気刺激策が企業収益を押し上げ、日本市場全体の魅力を高めると考えたのです。
しかし、この楽観的な雰囲気は、政権発足からわずか1ヶ月足らずで消え去ります。ブルームバーグは2025年11月20日の記事で、高市政権による歳出拡大が日本の財政を著しく悪化させるのではないかとの懸念が市場に広がったと報じています。その結果、投資家は日本資産を売却する動きを強め、国債利回りは急上昇し、円は対ドルで危険水域とされる水準まで下落が加速しました。日経平均株価も11月18日には4月以来の大幅な下落率を記録するなど、市場の陶酔感は完全に終焉を迎えたのです。
アシンメトリック・アドバイザーズの日本株ストラテジスト、アミール・アンバーザデ氏は、トレーダーらが当初歓迎していた景気刺激策が、今や自身の首を絞める状況になっていると指摘しています。同氏が「ハネムーン期間は終わった」と語るように、市場は政権の政策をより厳しい目で評価し始めており、期待先行の買いから現実的なリスク評価に基づく売りへと、そのスタンスを大きく転換させたと言えるでしょう。この急激な心理の変化こそが、現在の市場の不安定さを象徴しています。
1-2. 「トリプル安」とは何か?市場への影響を解説
市場で警戒されている「トリプル安」とは、一国の金融市場において「株安」「債券安」「通貨安」という三つの下落が同時に進行する現象を指します。これは、その国の経済や政策に対する国内外の投資家からの信認が、総合的に失われている状態を示す極めて深刻なシグナルです。それぞれの要素が相互に影響し合い、経済全体に負のスパイラルを引き起こす危険性を内包しているため、市場関係者はその兆候を強く警戒します。
まず「株安」は、企業の将来的な収益性に対する悲観的な見通しを反映します。株価が下落すると、企業の資金調達が困難になるだけでなく、個人投資家の資産価値が目減りする「逆資産効果」によって消費マインドが冷え込み、実体経済に悪影響を及ぼします。次に「債券安」は、国債価格の下落を意味し、これは長期金利の上昇と表裏一体の関係にあります。長期金利が上昇すると、企業は設備投資のための借入コストが増加し、個人は住宅ローンの金利負担が重くなるなど、経済活動全体を抑制する方向に作用します。
そして「通貨安」は、その国の通貨の価値が他国通貨に対して下落することです。通常、緩やかな円安は輸出企業の採算を改善させるため日本経済にとってプラスと見なされることもあります。しかし、国の信認低下を背景とした急激な通貨安は「悪い円安」と呼ばれ、輸入に頼るエネルギーや食料品の価格を高騰させ、国民生活を直接圧迫します。さらに、海外からの資金逃避を加速させる要因ともなり、株安や債券安をさらに助長する悪循環を生み出しかねません。これら三つの下落が同時に発生するトリプル安は、日本経済が直面する信認の危機を明確に示しているのです。
1-3. 政策への信認低下を招いた複数の要因
市場の信認が急速に低下した背景には、経済対策の規模に対する懸念だけではなく、高市政権が矢継ぎ早に打ち出した複数の政策方針が複合的に影響しています。ブルームバーグの記事によれば、投資家心理を冷え込ませた要因は財政拡張への不安にとどまらないと指摘されています。その一つが、基礎的財政収支(プライマリーバランス)黒字化の単年度目標を撤回したことです。これは財政規律を軽視しているとのメッセージとして市場に受け取られ、国債の信認を揺るがす大きな要因となりました。
さらに、企業統治指針を従来の株主重視から転換する方針を示したことも、海外投資家の不信感を招きました。日本のコーポレートガバナンス改革は、長年にわたり日本株の魅力を高める重要な要素と見なされてきました。この改革の流れに逆行するかのような方針転換は、日本市場への投資を躊躇させるのに十分な材料と見なされたのです。資本効率の改善や株主還元の強化といった流れが後退すれば、日本株を積極的に買い進める理由が失われてしまいます。
加えて、中国との外交摩擦を引き起こしたことも、地政学リスクを意識する投資家を動揺させました。日本にとって最大の貿易相手国である中国との関係悪化は、サプライチェーンの混乱や日本企業の収益悪化に直結する可能性があります。経済政策の不確実性に加え、外交リスクまで高まる状況は、投資家がリスク回避姿勢を強める原因となります。これら財政、企業統治、外交という複数の分野における一連の動きが重なり合い、高市政権の政策運営能力そのものに対する疑念を生み出し、深刻な信認低下につながったのです。
1-4. 過去の事例:英国「トラス・ショック」との比較
現在の日本市場が直面する状況を理解する上で、2022年に英国を襲った市場の混乱、いわゆる「トラス・ショック」が重要な参考事例となります。当時、就任直後のリズ・トラス首相が打ち出した大規模な減税策と財源の裏付けがない歳出拡大策は、市場から財政規律を無視したポピュリズム政策であると見なされました。その結果、英国の財政に対する信認が失墜し、英国債は暴落(金利は急騰)、通貨ポンドも対ドルで史上最安値を更新するなど、深刻なトリプル安に見舞われました。
ブルームバーグの記事でも、T&Dアセットマネジメントの浪岡宏チーフストラテジストが、日本の経済対策の規模によっては「トラス政権下の英国を襲った市場混乱の再現を懸念する」とコメントしています。この二つの事例には、いくつかの共通点が見られます。第一に、新政権が市場の期待を背負って発足した直後に、財政規律を度外視したかのような大規模な財政政策を打ち出した点です。第二に、その政策が市場との十分な対話なしに発表され、投資家に大きな不確実性と不信感を与えた点も共通しています。
もちろん、日本と英国では経済構造や背景に違いもあります。日本は世界最大の対外純資産国であり、国債のほとんどが国内で消化されているため、英国のように急激な資金流出が起きにくいという指摘もあります。しかし、グローバル化が進んだ現代の金融市場において、国内投資家だけで国債市場を支え続けることには限界があります。ひとたび財政への信認が本格的に損なわれれば、国内勢も国債売りを加速させる可能性は否定できません。トラス・ショックがわずか数週間で政権を退陣に追い込んだように、市場の信認を失うことの代償は極めて大きいことを、私たちは歴史から学ぶ必要があります。
2. 金融市場の混乱が不動産市況に与える影響
金融市場で進行しつつあるトリプル安の波は、株式や為替といった領域にとどまらず、私たちの生活に身近な不動産市況にも深刻な影響を及ぼす可能性があります。不動産市場は金利の動向に極めて敏感であり、また海外からの資金流入や国内の建築コストにも左右されるため、金融市場の混乱とは決して無関係ではありません。本章では、長期金利の上昇、円安の進行、そして投資家マインドの冷え込みという三つの側面から、トリプル安が不動産市況にどのような変化をもたらすのかを具体的に考察します。
2-1. 長期金利の上昇が住宅ローンに及ぼす直接的な打撃
トリプル安の一角をなす「債券安」は、長期金利の上昇を意味します。日本の長期金利の代表的な指標である新発10年物国債の利回りが上昇すると、金融機関はそれを基準に様々な貸出金利を決定するため、私たちの生活に直接的な影響が及びます。特に影響が大きいのが、住宅ローンの固定金利です。金融機関は、長期国債の利回りに一定のスプレッド(利ざや)を上乗せして住宅ローンの固定金利を設定しているため、国債利回りの上昇はほぼ自動的に固定金利の引き上げにつながります。
金利が上昇すれば、住宅購入希望者の毎月の返済額は増加し、総返済額も大きく膨れ上がることになります。例えば、数千万円規模の借り入れを行う住宅ローンでは、金利がわずか数パーセント上昇するだけで、総返済額は数百万円単位で増加するケースも少なくありません。これにより、これまで住宅購入を検討していた層が計画の見直しを迫られたり、購入自体を断念したりする可能性が高まります。結果として、住宅需要全体が減退し、不動産価格、特に実需層がターゲットとするファミリー向けマンションや戸建て住宅の価格には下落圧力がかかることが予想されます。
また、すでに変動金利で住宅ローンを組んでいる人々にとっても、長期金利の上昇は無視できない問題です。変動金利は短期プライムレートに連動しており、直接的には長期金利の影響を受けにくいとされています。しかし、長期金利の上昇が続く状況は、日本銀行による金融緩和策の修正、すなわち将来的な利上げが近いとの市場の観測を強めることになります。日銀が政策金利の引き上げに踏み切れば、変動金利も上昇を避けられません。金利上昇局面では、住宅購入に対する消費者のマインドは著しく冷え込み、不動産市況全体を停滞させる大きな要因となるのです。
2-2. 円安の二面性:海外投資家と国内コスト
トリプル安のもう一つの要素である「円安」は、不動産市況に対して二つの異なる側面から影響を与えます。一つは、海外投資家にとっての価格的な魅力が増すというポジティブな側面です。円の価値がドルや他の主要通貨に対して下落すると、海外の投資家は以前よりも少ない自国通貨で日本の不動産を購入できるようになります。つまり、日本の不動産が相対的に割安になるため、海外からの投資マネーが流入しやすくなるのです。特に、政治的に安定し、高い品質を持つ東京などの都心部の高級物件は、魅力的な投資対象として注目を集める可能性があります。
しかし、円安には国内の不動産市場にとって極めて深刻なネガティブな側面も存在します。それは、建築コストの高騰です。日本は、木材や鉄鉱石、アルミニウムといった建築資材の多くを輸入に頼っています。円安が進行すると、これらの輸入資材の円建て価格が上昇し、建築コスト全体を押し上げることになります。すでに世界的なインフレやサプライチェーンの混乱によって資材価格は高騰していましたが、悪い円安がこれに拍車をかける形となります。建設会社は上昇したコストを販売価格に転嫁せざるを得ず、特に新築マンションや新築戸建ての価格はさらに上昇することが避けられません。
この結果、国内の一般的な所得層にとっては、新築物件がますます手の届かない存在となってしまう可能性があります。前述の住宅ローン金利の上昇と、この建築コスト高騰による物件価格の上昇が同時に起これば、国内の実需はダブルパンチを受けることになります。一方で、海外の富裕層や機関投資家は、円安メリットを享受して都心部の高額物件を購入する。このように、円安は国内需要を冷え込ませながら海外からの投資を呼び込むことで、不動産市場の二極化を一層加速させる要因となり得るのです。
2-3. 投資家マインドの冷え込みと二極化の可能性
金融市場全体の不確実性が高まると、不動産投資家のマインドも必然的に冷え込みます。トリプル安が示すような国への信認低下は、投資家にとって最大のリスクです。将来の経済成長が見通せず、金利も上昇局面にある中では、リスクを取って新たな不動産投資に踏み切る動きは鈍化せざるを得ません。特に、地方都市や郊外の収益物件など、比較的リスクが高いとされる不動産からは資金が引き揚げられやすくなります。空室率の上昇や賃料の下落懸念が高まり、投資妙味が薄れるためです。
融資環境の厳格化も、投資家マインドを冷え込ませる大きな要因となります。長期金利が上昇し、金融市場が不安定化する局面では、金融機関は貸し出しに対するリスクをより慎重に評価するようになります。不動産投資向けの融資審査は厳しくなり、自己資金の割合を多く求められたり、融資自体を断られたりするケースが増加します。これにより、これまでレバレッジを効かせて物件を買い進めてきた投資家たちの活動は大きく制限されることになります。結果として、不動産取引量そのものが減少し、市場全体の流動性が低下する可能性も考えられます。
これらの要因が重なることで、不動産市場では「二極化」が一層鮮明になると予想されます。一方で、海外投資家や国内の富裕層は、円安やインフレヘッジの観点から、資産価値が毀損しにくいとされる東京都心部の一等地やタワーマンションなどの「安全資産」に資金を集中させるでしょう。他方で、国内の実需層がターゲットとする郊外の物件や、地方の収益物件は、金利上昇と需要減退の影響を直接的に受け、価格が伸び悩むか、あるいは下落する可能性があります。このように、トリプル安は不動産市場を一枚岩として捉えることを困難にし、エリアや物件種別による格差を拡大させる深刻な影響を及ぼすのです。
3. 日本経済の行方を占う今後のシナリオ分析
高市政権の政策運営と市場の反応が交錯する中、日本経済は極めて重要な岐路に立たされています。現在の混乱が一時的なものに終わるのか、それとも構造的な危機へと発展するのかは、今後の政府・日本銀行の対応次第と言えるでしょう。ブルームバーグの記事で示された専門家の見解を基に、今後想定される三つの主要なシナリオを分析し、それぞれの展開が日本経済に何をもたらすのかを深く考察します。
3-1. 最悪のシナリオ:財政規律の喪失と市場の混乱
最も懸念されるのは、政府が市場の警告を顧みず、財政規律を度外視した大規模な経済対策を強行するシナリオです。ブルームバーグの記事では、一部の自民党議員から25兆円規模の補正予算を求める声が上がっていることが報じられています。もしこのような巨額の財政出動が現実のものとなれば、日本の財政に対する信認は決定的に失われ、トリプル安がスパイラル的に悪化する可能性があります。これは、2022年の英国「トラス・ショック」の再現、あるいはそれ以上の混乱を招きかねません。
このシナリオでは、まず国債市場で売りが殺到し、長期金利は制御不能な水準まで急騰します。金利上昇は企業の設備投資や個人の住宅ローンを直撃し、実体経済は急速に冷え込むでしょう。同時に、日本売りは為替市場にも波及し、円は1ドル=160円といった節目を軽々と突破し、さらなる下落を続ける可能性があります。急激な円安は輸入物価の高騰を通じて激しいインフレーションを引き起こし、国民の生活を著しく圧迫します。
企業業績も、コストプッシュインフレと内需の冷え込みというダブルパンチを受け、大幅に悪化することが予想されます。そうなれば、株価はさらなる下落を余儀なくされるでしょう。RBCブルーベイ・アセット・マネジメントの最高投資責任者(CIO)、マーク・ダウディング氏が「もし高市首相が政策面での信認を失えば、投資家は日本資産の全てを売り始めるだろう」と警告するように、このシナリオは日本経済全体が深刻なスタグフレーション(景気後退とインフレの同時進行)に陥るリスクをはらんでいます。
3-2. 安定化シナリオ:政策修正による信頼回復
次に考えられるのは、市場からの強い圧力と警告を受け、政府が政策方針を柔軟に修正し、市場との対話を通じて信頼回復を図るシナリオです。この展開では、政府は経済対策の規模を市場が許容できる範囲に抑制し、その財源についても国債の追加発行を極力抑えるなど、財政規律に配慮した姿勢を明確に打ち出します。同時に、撤回したプライマリーバランス黒字化目標に代わる、新たな財政再建の道筋を具体的に示すことが求められます。
市場の信認を回復するためには、政策の一貫性と透明性が不可欠です。企業統治指針の転換や外交方針など、投資家の不信感を招いた他の政策についても、その意図を丁寧に説明し、市場の懸念を払拭する努力が必要となるでしょう。政府と日本銀行が緊密に連携し、金融市場の安定を最優先する姿勢を明確にすれば、投資家心理は徐々に落ち着きを取り戻すと考えられます。
このシナリオが実現した場合、急騰していた長期金利は安定し、円安の進行にも歯止めがかかります。株式市場も、政策の不確実性が後退したことを好感し、反発に転じる可能性があります。トリプル安の危機は回避され、日本経済は再び安定した成長軌道に戻るための土台を築くことができます。ただし、一度損なわれた信頼を完全に取り戻すには時間がかかります。このシナリオは、政権が市場の声に真摯に耳を傾け、現実的な政策運営へと舵を切ることができるかどうかにかかっています。
3-3. 成長実現シナリオ:財政出動が経済を押し上げる可能性
最後に、短期的には市場の混乱を招きつつも、最終的に政府の積極的な財政出動が功を奏し、日本経済を本格的な成長軌道に乗せるというポジティブなシナリオも考えられます。このシナリオでは、大規模な経済対策によって喚起された需要が、企業の設備投資や賃上げを促進し、個人消費を活性化させるという好循環が生まれます。長年日本経済を苦しめてきたデフレマインドが完全に払拭され、経済が持続的なインフレと成長を実現する展開です。
ブルームバーグの記事の結びでは、キャピタル・エコノミクスのアジア太平洋市場統括責任者、トマス・マシューズ氏の見解が紹介されています。同氏は、高市首相の財政刺激策が実行されて景気が過熱し始めれば、日本銀行による利上げは避けられなくなると指摘しています。金融引き締めへの転換は、すなわち日本経済が金融緩和という特別な措置を必要としない、正常な状態に戻ったことを意味します。
出展: ブルームバーグ「高市政権襲う「トリプル安」、予算膨張警戒で市場陶酔に終止符も」
景気の過熱とそれに伴う日銀の利上げは、日本の金利を上昇させ、日米金利差の縮小を通じて円高要因となります。マシューズ氏は「そうなれば来年には円が急反発する可能性がある」とみており、一時的な混乱を経て、最終的には日本経済のファンダメンタルズ(基礎的条件)が改善され、日本資産が内外の投資家から再評価されるという見方です。このシナリオは、政府の政策が市場の懸念を乗り越え、実体経済に力強いプラスの効果をもたらすという、最も望ましい未来像と言えるでしょう。しかし、その実現には、政策の的確な実行と幸運が伴う必要があります。
4. 不確実な時代を乗り切るための個人としての備え
金融市場が大きな変動に見舞われる中、私たち個人はただ状況を傍観するだけでなく、自らの資産と生活を守るために適切な備えをしておくことが極めて重要になります。政府の政策や市場の動向を完全に予測することは誰にもできませんが、起こりうるリスクを想定し、事前に対策を講じることは可能です。本章では、投資家や住宅購入を検討している方々が、この不確実な時代を乗り切るために取るべき具体的なアクションについて解説します。
4-1. ポートフォリオの見直しとリスク管理
現在のような市場のボラティリティ(変動率)が高まっている局面では、まず自身が保有している資産、すなわちポートフォリオの内容を再点検することが不可欠です。特定の資産、例えば日本株や日本円に資産が過度に集中している場合、トリプル安のような状況では大きな損失を被るリスクが高まります。リスクを分散させるためには、資産を国内外の株式、債券、不動産、コモディティ(商品)などに幅広く配分する「国際分散投資」の原則に立ち返ることが重要です。
特に、円安リスクに備えるためには、資産の一部をドルやユーロといった外貨建ての資産で保有することが有効な手段となります。外貨預金や外国株式、外国債券などをポートフォリオに組み入れることで、円の価値が下落した際に、その損失を外貨建て資産の値上がりで相殺する効果が期待できます。また、金利上昇局面では、債券価格は下落する傾向があるため、債券への投資比率やその種類(年限の長さなど)を見直すことも検討すべきでしょう。
最も重要なのは、自身がどの程度のリスクを取れるのかという「リスク許容度」を再確認することです。年齢や家族構成、収入、そして性格によって、取れるリスクの大きさは人それぞれ異なります。市場が不安定な時こそ冷静になり、自身の許容度を超えたリスクを取っていないかを確認し、必要であればリバランス(資産配分の調整)を行うことが、長期的な資産形成の成功につながります。短期的な市場の動きに一喜一憂せず、長期的な視点に立った資産管理を心掛けることが求められます。
4-2. 不動産購入を検討する際の注意点
これから住宅の購入を検討している方にとって、現在の市場環境は非常に判断が難しい局面と言えます。長期金利の上昇は、住宅ローンの固定金利に直接的な影響を及ぼし、将来の返済負担を増大させるリスクがあります。このような状況下で住宅購入を検討する際には、いくつかの点を慎重に考慮する必要があります。まず、金利タイプの選択です。今後の金利上昇リスクを避けたいのであれば、返済額が完済まで変わらない全期間固定金利型の住宅ローンを選択することが賢明です。
次に、無理のない返済計画を立てることがこれまで以上に重要になります。将来の金利上昇や、予期せぬ収入の減少など、不測の事態にも対応できるよう、自己資金(頭金)をできるだけ多く用意し、借入額を抑えることが望ましいです。一般的に、年間の返済額が年収に占める割合(返済負担率)は25%以内が目安とされていますが、より保守的に20%程度に抑えて計画を立てると安心感が増すでしょう。
また、物件価格の動向も慎重に見極める必要があります。前述の通り、建築コストの高騰により新築物件の価格は上昇傾向にありますが、一方で金利上昇による需要減退が中古物件の価格を下押しする可能性もあります。焦って購入を決めるのではなく、市場の動向を注意深く観察し、複数の物件を比較検討する時間を十分に取ることが大切です。信頼できる不動産会社やファイナンシャルプランナーに相談し、客観的なアドバイスを求めることも、後悔のない選択をするために有効な手段となるでしょう。
4-3. 最新の経済ニュースを注視する重要性
このような不確実性の高い時代において、個人ができる最も基本的かつ重要な対策は、信頼できる情報源から最新の経済ニュースを継続的に収集し、正しく理解することです。政府が発表する経済対策の具体的な内容、日本銀行の金融政策決定会合の結果、そして国内外の金融市場の動向など、自身の資産や生活に影響を与える可能性のある情報は数多く存在します。特定のメディアの論調に偏ることなく、複数の情報源を比較検討し、客観的な事実を把握するよう努めることが重要です。
例えば、ブルームバーグやロイターといった国際的な通信社、日本経済新聞などの専門紙、あるいは公的機関が発表する統計データなどは、信頼性の高い情報源と言えます。これらの情報を日々確認することで、市場が何を懸念し、何を期待しているのかという大きな流れを掴むことができます。経済指標や金融用語など、最初は難しく感じるかもしれませんが、継続的に触れることで徐々に理解が深まっていきます。
情報を収集する目的は、市場の短期的な動きを予測して利益を得ることではありません。むしろ、中長期的な視点で世の中の構造的な変化を捉え、自身のライフプランや資産形成の方針を適切に見直していくための判断材料を得ることにあります。変化の激しい時代だからこそ、情報を自ら能動的に取りに行き、冷静に分析する姿勢が、個人の資産と生活を守るための最強の武器となるのです。
*出展: ブルームバーグ「高市政権襲う「トリプル安」、予算膨張警戒で市場陶酔に終止符も」
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-11-19/T5YMI8T96OSG00