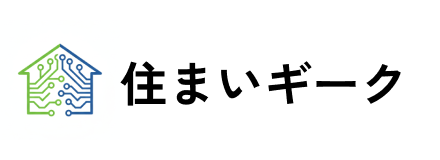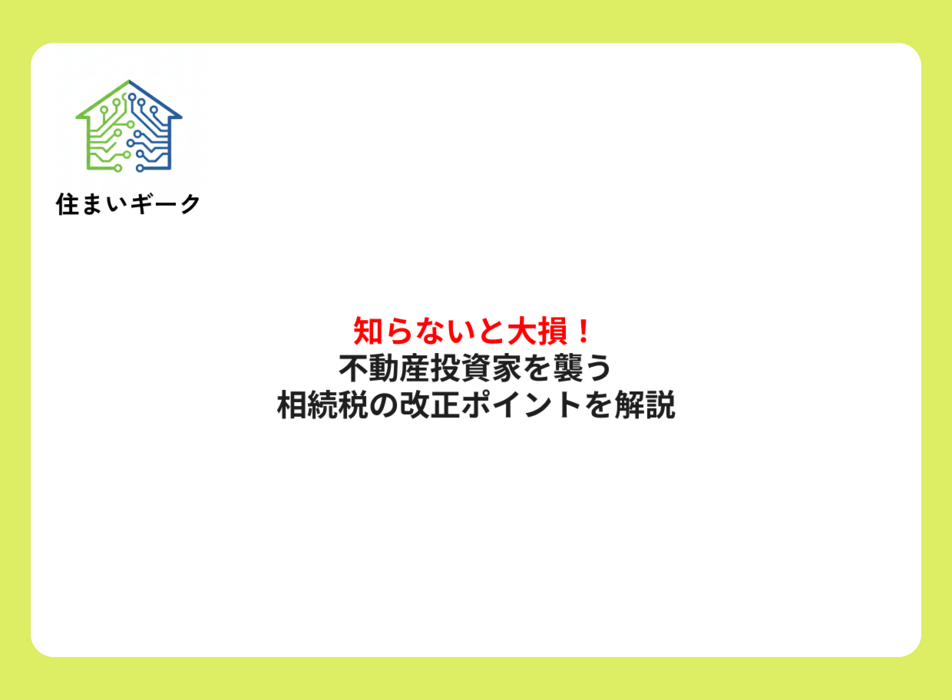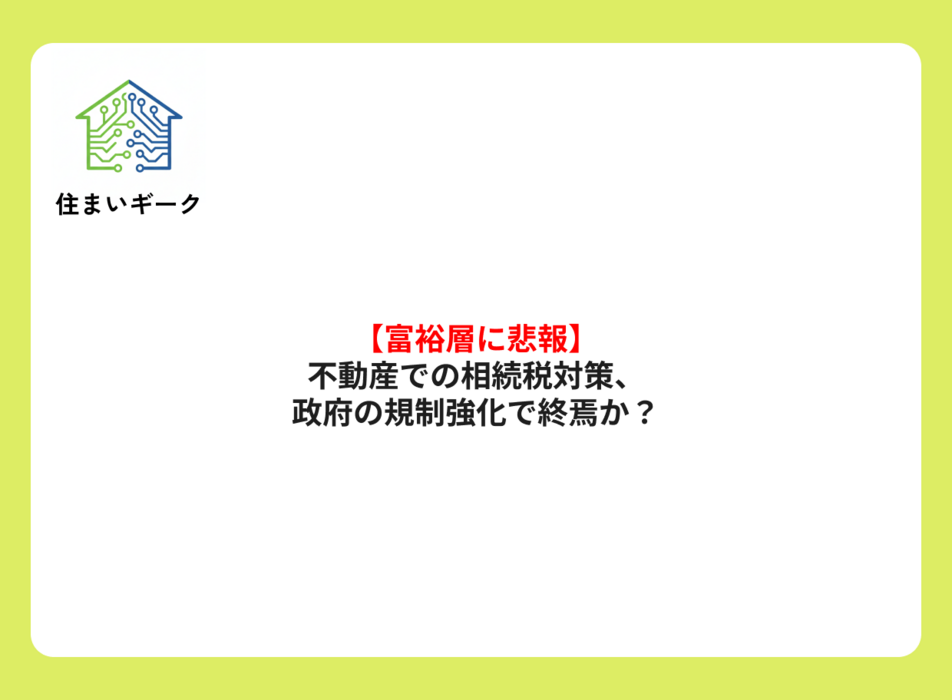1. 投資用不動産の相続税評価額見直しの概要
1-1. 政府・与党が検討する新たな評価方法とは
政府および与党は、投資用不動産を対象とした相続税の算定方法に関して、抜本的な見直しを行う具体的な検討段階に入りました。今回の改正案の結論は、相続直前に購入された物件の評価額を、実勢価格に近い購入価格に基づいて算定するというものです。これにより、これまで可能であった相続税の圧縮効果が大きく制限されることになり、不動産投資家の戦略に影響を与えます。
現行の制度では、不動産を相続する際の評価額は、主に国税庁が定める路線価や市町村が管理する固定資産税評価額を基に算出されます。これらの評価額は、一般的に市場で取引される実勢価格、いわゆる時価の7割から8割程度の水準に設定されているのが実情です。この時価と評価額の間に生じる差額を利用することで、現金を不動産に換えて相続財産の評価額を圧縮し、結果的に相続税の負担を軽減する手法が広く活用されてきました。
しかし、日本経済新聞が報じた政府・与党の改正案では、この仕組みに大きな変更が加えられることになります。具体的には、被相続人が生前に投資用不動産を購入してから、一定の期間内に相続が発生したケースが対象とされます。その場合、従来の路線価などによる評価ではなく、その不動産の購入時の価格を基に相続税評価額を算定するルールが導入される見込みです。この「一定の期間」については、購入から5年以内の相続を軸として現在調整が進められています。
この変更が実現すれば、例えば相続発生の3年前に5億円で購入した投資用マンションは、相続時の評価額も5億円に近い金額となります。現行制度であれば時価の7割から8割程度、つまり3億5,000万円から4億円程度に評価額が圧縮される可能性があったため、納税者にとっては大幅な税負担の増加につながることを意味します。この改正は、特に相続税対策を主目的とした不動産購入に歯止めをかける強い意図が込められていると言えます。
出展: 日本経済新聞「投資用マンション節税に歯止め、相続直前購入なら税重く 政府・与党検討」
1-2. なぜ今、税制改正が議論されるのか
このタイミングで相続税に関する税制改正が議論される背景には、大きく分けて二つの重要な要因が存在していると考えられます。第一の要因は、課税の公平性を確保するという社会的な要請です。そして第二の要因として、近年の司法判断が示した「行き過ぎた節税」に対する警鐘が、法改正を後押しする形となったことが挙げられます。
まず課税の公平性についてですが、現行制度を利用した不動産による相続税対策は、主に多額の現預金を保有する富裕層が活用してきました。特に、時価と相続税評価額の乖離が大きい都市部のタワーマンションなどは、その節税効果の高さから人気を集めていました。しかし、この手法は多額の資金を持つ一部の層のみが享受できる恩恵であり、一般の納税者との間に不公平感を生じさせているとの指摘が以前からありました。
政府・与党としては、特定の資産を持つ者だけが税負担を大幅に軽減できる現状を問題視し、誰もが納得できる公平な税制を構築する必要があると考えています。今回の改正案は、こうした資産格差に起因する課税の歪みを是正し、税負担の公平性を確保することで、国民の税制に対する信頼を取り戻す狙いがあるのです。税は能力に応じて公平に負担するという「応能負担の原則」に立ち返る動きと言えるでしょう。
もう一つの重要な背景が、2022年4月に最高裁判所が下した判決です。この裁判では、相続直前に購入された不動産の評価を巡り、国税庁が路線価による評価を否認し、不動産鑑定評価額(時価に近い価格)で追徴課税した処分の妥当性が争われました。最高裁は、他の納税者との間の実質的な租税負担の公平を著しく害する「特別な事情」がある場合、路線価による画一的な評価は相当ではないとの判断を示しました。
この判決は、形式的には合法であっても、その実態が租税回避目的であることが明らかな場合には、税務当局がより実態に即した評価を行うことを認めるものでした。この司法判断は、行き過ぎた節税行為に対して国が介入する正当性を裏付ける強力な根拠となり、今回の具体的な法改正に向けた議論を加速させる大きなきっかけとなったのです。つまり、司法の判断を立法措置によって明確なルールとして整備する動きが本格化したと言えます。
2. 現行制度の問題点と「タワマン節税」の実態
2-1. 相続税評価額の算出方法と時価との乖離
現行の相続税法において、土地の評価は原則として「路線価方式」または「倍率方式」によって行われます。都市部の宅地の多くで採用される路線価方式では、国税庁が毎年公表する主要な道路に面した土地1平方メートルあたりの価格(路線価)を基に、土地の形状などに応じた補正を加えて評価額を算出します。この路線価は、地価公示価格や売買実例価格などを基に算定されますが、その水準は公示価格の80%程度に設定されています。
一方、建物の評価額は、市町村が管理する固定資産税台帳に登録された「固定資産税評価額」がそのまま用いられます。この固定資産税評価額は、再建築価格(同じ建物を新築した場合にかかる費用)を基に、経年劣化による減価を考慮して算出されます。その水準は、一般的に建築費のおおよそ50%から70%程度とされており、市場での取引価格、つまり時価とは大きく異なることが少なくありません。
このように、土地は時価の約8割、建物は建築費の5割から7割で評価されるため、不動産全体の相続税評価額は、必然的に市場での実勢価格よりも低い金額となります。例えば、時価1億円の不動産(土地5,000万円、建物5,000万円)があった場合を想定してみましょう。土地の評価額は8割の4,000万円、建物の評価額は仮に6割とすると3,000万円となり、合計の評価額は7,000万円となります。
この場合、現金1億円を相続するよりも、不動産に換えて相続した方が評価額を3,000万円も圧縮できる計算になります。相続税は課税遺産総額に税率を掛けて算出されるため、評価額が低くなるほど税負担は軽くなります。この時価と相続税評価額の間に存在する乖離こそが、相続税対策として不動産が活用される根本的な理由であり、今回の税制改正がメスを入れようとしている核心部分なのです。
2-2. いわゆる「タワマン節税」の仕組みと背景
「タワマン節税」とは、時価と相続税評価額の乖離が特に大きくなりやすいタワーマンションの特性を利用した相続税対策の通称です。この手法が大きな節税効果を生む背景には、マンションの評価額を算出する際の特殊な計算方法が関係しています。マンションのような区分所有建物の評価は、土地と建物を別々に算出し、それらを合算して行われます。
まず、土地(敷地権)の評価額ですが、マンションが建つ敷地全体の評価額を算出した後、それを各戸の専有部分の面積割合に応じて按分します。タワーマンションは一つの敷地に多数の住戸が存在するため、一戸あたりの土地の持ち分は非常に小さくなります。その結果、土地全体の価格が高くても、一戸あたりの土地評価額は比較的低く抑えられる傾向にあります。
次に、建物の評価額は、固定資産税評価額が基になりますが、ここがタワマン節税の最も重要なポイントとなります。マンションの固定資産税評価額は、建物の階数に関わらず、専有部分の面積が同じであれば、原則としてどの階でも同じ評価額となるのです。しかし、実際の市場価格、つまり時価は、一般的に低層階よりも高層階の方が眺望などの付加価値から高額で取引されます。
例えば、同じ面積の部屋でも、2階の部屋の時価が5,000万円であるのに対し、40階の部屋は1億円で取引されることがあります。しかし、相続税の算定基礎となる建物の評価額は、どちらも同じ金額になってしまうのです。この結果、高層階の部屋ほど時価と評価額の乖離が極端に大きくなり、現金で購入した場合と比較して、相続財産を劇的に圧縮できるという現象が生まれます。これが「タワマン節税」の基本的な仕組みです。
この仕組みを利用し、相続が近い富裕層がタワーマンションの高層階を現金で購入し、相続後に売却して再び現金に戻すといった行為が一部で行われてきました。こうした行為は、実質的な資産価値を減らすことなく、納税額だけを不当に低くする行為であると見なされ、課税の公平性を著しく損なうものとして社会的な批判を浴びる原因となっていました。
3. 税制改正が不動産投資市場に与える影響
3-1. 相続税対策を目的とした投資家への直接的な影響
今回の税制改正案が原案に近い形で導入された場合、相続税対策を主目的として不動産投資を行ってきた、あるいは検討していた投資家層に極めて直接的かつ大きな影響を及ぼします。結論から言えば、相続発生直前の駆け込み購入による節税スキームは、その有効性をほぼ失うことになります。これにより、投資家の投資判断基準は大きな転換を迫られることになるでしょう。
改正案の核心は、購入から5年以内といった短期間で相続が発生した場合、相続税評価額を時価に近い購入価格で算定するという点にあります。これは、これまで最大のメリットとされてきた「財産評価額の圧縮効果」が、少なくとも購入後数年間は期待できなくなることを意味します。そのため、相続税の軽減のみを狙って、収益性や資産価値を度外視した不動産投資を行うインセンティブは著しく低下します。
例えば、これまでであれば相続が予見される段階で、金融資産を評価額の低い不動産に組み替えるという選択肢が有効でした。しかし改正後は、購入後すぐに相続が発生してしまうと、不動産に換えても評価額がほとんど変わらないため、節税メリットが生まれません。それどころか、不動産取得税や登記費用、仲介手数料といった諸経費がかかる分、かえって資産が目減りするリスクすら考えられます。
この変化は、不動産投資家に対して、より本質的な投資価値を見極める目を要求することになります。短期的な節税効果という視点から解放され、その物件が長期的に安定した家賃収入(インカムゲイン)を生み出すか、将来的に価値が上昇する見込み(キャピタルゲイン)があるかといった、不動産投資本来の収益性や資産性がより重視されるようになります。結果として、相続対策を検討する投資家は、ポートフォリオの全面的な見直しを迫られることになるでしょう。
3-2. 不動産市況への短期的な影響と長期的な影響
税制改正は、個々の投資家だけでなく、不動産投資市場全体にも少なからぬ影響を与えることが予想されます。その影響は、法制化が具体化するまでの短期的な視点と、制度が定着した後の長期的な視点で分けて考える必要があります。短期的には、一部で駆け込み需要が発生した後、関連市場が一時的に停滞する可能性があります。
まず短期的な影響として、改正が施行される前に節税メリットを享受しようとする「駆け込み購入」が、一部の富裕層の間で発生する可能性が考えられます。特に、時価と評価額の乖離が大きい都心部のタワーマンションや高額な収益物件において、一時的に需要が高まるかもしれません。ただし、改正の議論が始まったことで、すでに市場は警戒感を強めており、その動きは限定的となる可能性もあります。
そして改正法の施行後は、これまで市場を支えてきた相続税対策目的の資金流入が減少するため、特に高額な投資用不動産の市場は一時的に需要が減退し、価格が調整局面に入る可能性があります。これまで過度な節税需要によって価格が押し上げられていた物件については、その需要が剥落することで、本来の収益性に基づいた価格水準へと落ち着いていくプロセスが想定されます。
一方で長期的な視点で見れば、この税制改正は不動産市場の健全化に寄与する側面も持ち合わせています。節税目的という特殊な需要が減少することで、市場はより物件本来の収益性や立地、建物の質といったファンダメンタルズに基づいて評価されるようになります。これは、実需に基づいた健全な価格形成を促し、バブル的な価格高騰のリスクを抑制する効果が期待できます。
また、投資家がより長期的な視点で物件を評価するようになるため、管理状態が良好で、長期的に安定した収益が見込める優良な物件の価値が相対的に高まる可能性があります。結果として、市場全体が投機的な色彩を薄め、より安定的で持続可能な成長を目指す健全な市場へと変貌していくきっかけになるかもしれません。
4. 今後の展望と個人投資家が備えるべきこと
4-1. 考えられる複数のシナリオと法制化までの道のり
今回報じられた税制改正案は、まだ政府・与党内での検討段階であり、最終的に法制化されるまでにはいくつかのプロセスを経る必要があります。その過程で、当初の案から内容が修正される可能性も十分に考えられ、投資家としては今後の動向を注意深く見守る必要があります。現時点で考えられる主なシナリオは、原案に近い形での導入、適用条件が緩和される形での導入、そして段階的な導入の三つです。
第一のシナリオは、報道の通り「購入から5年以内」という基準を軸に、大きな変更なく法制化されるケースです。この場合、相続税対策を目的とした不動産投資への影響は最も大きくなり、市場に与えるインパクトも明確になります。政府・与党が課税の公平性を強く重視するならば、このシナリオの実現可能性は高いと言えるでしょう。
第二のシナリオは、不動産業界や市場への急激な影響を緩和するため、適用条件が調整されるケースです。例えば、対象期間が「5年」から「3年」に短縮されたり、対象となる不動産が時価と評価額の乖離が特に大きい一定額以上の物件やタワーマンションなどに限定されたりする可能性が考えられます。これにより、影響範囲を絞り込み、市場の混乱を最小限に抑えようとする調整が行われるかもしれません。
第三のシナリオとして、経過措置を設けたり、段階的に制度を導入したりする可能性も挙げられます。例えば、施行後数年間は購入価格と路線価評価額の中間の値で評価するなど、納税者の負担が急増しないような緩和措置を設ける方法です。また、初年度は対象期間を短く設定し、年々その期間を延長していくといった段階的な導入も、市場の軟着陸を図る上では有効な手段となり得ます。
今後の具体的な流れとしては、年末に策定される与党の「税制改正大綱」でその骨格が示され、年明けの通常国会で関連法案が審議されることになります。投資家は、これらのプロセスで公表される情報を常に収集し、最終的にどのような形で制度が決定されるのかを正確に把握することが重要です。
4-2. 投資家が今から準備すべき具体的な対策
この税制改正の動きを受けて、不動産投資家、特に相続を視野に入れている方は、今後の戦略を再構築するために今から準備を始めることが賢明です。重要なのは、短期的な節税効果に依存するのではなく、長期的かつ多角的な視点から資産防衛と資産形成を考えることです。具体的な対策としては、資産ポートフォリオの見直しや、不動産以外の相続対策の検討などが挙げられます。
まず行うべきは、現在保有している、あるいはこれから購入を検討している不動産の投資目的を再確認することです。もしその目的が相続税対策に大きく偏っているのであれば、その物件の収益性や資産価値を改めて客観的に評価し直す必要があります。安定した家賃収入が見込めない物件や、将来的な売却が難しい物件であれば、資産の組み換え、つまり売却してより優良な資産に換えることも選択肢に入れるべきでしょう。
次に、不動産だけに頼らない多様な相続対策を検討することが重要になります。例えば、生命保険の活用は有効な手段の一つです。「500万円 × 法定相続人の数」という生命保険金の非課税枠を利用すれば、相続税の課税対象となる財産を減らすことができます。また、年間110万円の基礎控除内で行う暦年贈与や、相続時精算課税制度を利用した生前贈与も、次世代へスムーズに資産を移転するための有力な選択肢となります。
さらに、法人化による資産管理も検討に値します。個人で不動産を所有するのではなく、資産管理会社を設立して法人名義で所有・管理することで、個人の相続財産から切り離すことが可能になります。法人の株式を相続することにはなりますが、役員報酬や退職金の活用など、所得税対策と組み合わせることで、総合的な税負担を最適化できる可能性があります。ただし、法人設立・維持にはコストがかかるため、専門家と相談の上で慎重に判断する必要があります。
4-3. Q&Aでわかる相続税評価額見直しのポイント
Q1. この税制改正は、いつから始まる見込みですか?
A1. 日本経済新聞の報道によれば、2022年内に政府・与党が改正案をまとめ、2023年度以降の税制改正大綱に盛り込むことを目指すとされています。具体的な施行時期は、今後の国会での審議を経て決定されますが、一般的には大綱で示された翌年度、あるいは翌々年度の1月1日以降に発生した相続から適用されるケースが多いです。
Q2. すでに所有している投資用不動産も、この改正の対象になりますか?
A2. 改正案の詳細は未定ですが、一般的に税制改正では、法律の不遡及の原則から、施行日より前に行われた行為(この場合は不動産の購入)に遡って新しいルールを適用することは考えにくいです。しかし、「施行日以降に発生した相続」が対象となり、その相続財産に「購入から5年以内の不動産」が含まれる場合に新ルールが適用される、という形になる可能性はあります。今後の詳細な制度設計を注視する必要があります。
Q3. 自分が住むための自宅マンションも対象になるのでしょうか?
A3. 今回の改正案は、あくまで「投資用不動産」を対象として検討されています。したがって、被相続人が自己の居住用として使用していた自宅マンションや戸建てについては、対象外となる可能性が高いと考えられます。改正の目的が、過度な節税を目的とした不動産投資の抑制にあるため、実需に基づいた居住用不動産にまで規制を広げることは想定しにくい状況です。
Q4. 「購入から5年以内」という期間は確定事項ですか?
A4. 「5年」という期間は、報道によれば政府・与党が「軸に調整する」としている段階であり、確定事項ではありません。今後の議論の過程で、不動産市場への影響や過去の判例などを考慮し、3年や7年など、より短い期間や長い期間に修正される可能性は十分にあります。最終的な期間は、年末に公表される税制改正大綱で明らかになる見込みです。